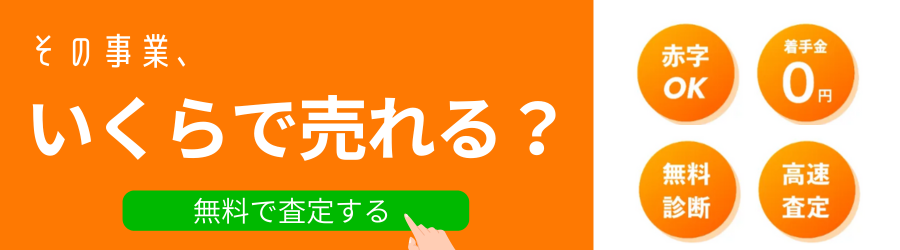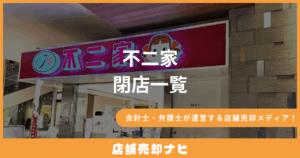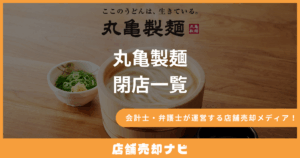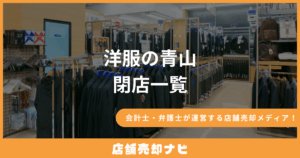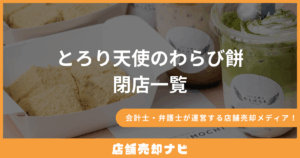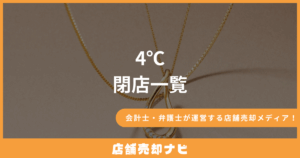飲食業界は競争が激しく、たとえ一時的に成功を収めた店舗でも、売上不振や人材不足、立地条件の変化といった要因で経営が立ち行かなくなることがあります。そんなとき、「撤退=失敗」と捉えてしまうと、冷静な判断ができずに損失を膨らませてしまうリスクもあります。
この記事では、撤退をネガティブな結末ではなく、「未来へつなげる前向きな判断」として位置付ける視点から、閉店やM&Aといった選択肢について解説していきます。
このページでわかること
- 飲食店が「戦略的撤退」を考えるべき背景と理由
- 損失を最小限に抑えるための撤退判断の基準と準備
- 閉店以外の選択肢としてのM&Aの可能性と進め方
- 撤退に関わる実務的な手続きや注意点
なぜ「戦略的撤退」が必要なのか
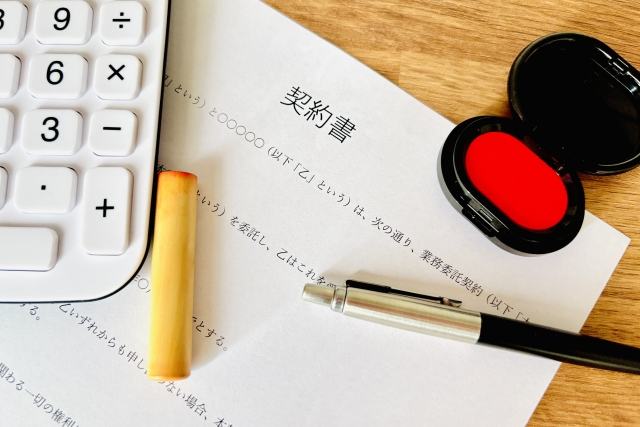
飲食店を経営していく中で、常に右肩上がりの成長が続くとは限りません。むしろ、赤字の長期化や人材の確保が困難になるなど、撤退を検討せざるを得ない状況に直面する経営者も多いのが現実です。「もう限界」となる前に、自らの意思で「戦略的撤退」という判断を下すことも大事になるでしょう。
飲食業界を取り巻く現状と経営の難しさ
コロナ禍以降、飲食業界はかつてない逆風にさらされています。売上の不安定さ、人材不足、原材料費の高騰、そして競合の激化。どれか一つでも苦しい状況が、複数同時に重なるケースも少なくありません。
そうした中、現場の声をもとに経営に影響を与えている主な要因を整理しました。
| 経営を圧迫する要因 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 人手不足 | 営業時間短縮・スタッフ負担増によるサービス低下 |
| 物価・光熱費の高騰 | 仕入原価の上昇で利益率が悪化 |
| 立地条件の変化 | 再開発・競合出店で来客数が減少 |
| 顧客の消費行動の変化 | 外食控えやデリバリー移行で来店数減 |
これらはすべて、店舗単体では解決しづらい構造的な問題です。だからこそ、経営判断としての撤退が必要になるケースが増えているのです。
撤退を選択する3つの主な理由
戦略的撤退を検討するに至った背景には、多くの店舗に共通する「明確な引き金」があります。特に多く見られるのが、以下の3点です。
- 売上・利益の長期的な低迷
↳黒字転換の見込みが立たない状況が続くと、撤退の検討が現実味を帯びてくる - 人手不足・従業員の確保難
↳営業を続けたくても人員が安定せず、クオリティの維持が困難になる - 立地・環境の変化
↳再開発や周辺環境の変化により、かつての集客力を維持できなくなる
このような状況が単独で発生するだけでなく、複合的に重なることで撤退の判断が現実的なものになります。

飲食店における戦略的撤退判断の基準と準備

飲食店を閉じる決断は、感情だけでなく数字と現実に基づいた冷静な判断が求められます。
売上や損益のデータを正しく把握し、どのタイミングで撤退するべきか、そしてその準備にどれだけ時間と労力が必要かを見極めることが重要です。
撤退の判断基準とは(売上・損益・立地など)
撤退の決断を下すには、主観だけでなく客観的な基準が必要です。継続すべきかどうかを判断する際にチェックしたい主な指標を表にまとめました。
| 判断項目 | 見るべきポイント | 撤退判断の目安 |
|---|---|---|
| 売上 | 月次・前年同月比・繁閑の変化 | 6ヶ月連続で前年同月比80%未満 |
| 損益 | 営業利益・経常利益の推移 | 半年以上赤字が続いている |
| キャッシュフロー | 資金繰り・運転資金の余力 | 1ヶ月先の支払いが不安 |
| 立地・環境 | 周辺の再開発、競合の出店状況 | 来店数の減少が明らか |
これらの指標は組み合わせて総合的に判断すべきものであり、どれか一つに極端な傾向が見えた場合には注意が必要です。

撤退時にかかるコストの具体例
撤退を決めた後に思わぬ出費が重なると、経営再建の足かせになります。費用の見通しを早期に立てておくことが大切です。飲食店の閉店にかかる代表的なコストには、以下のようなものがあります。
- 原状回復費用
↳内装・設備の撤去や修復にかかる費用 - 契約解除料・保証金清算
↳テナント契約に基づく違約金や返還対象外の保証金 - 従業員関連費用
↳最終給与、退職金、社会保険料など - 在庫・設備の処分費用
↳残った食材や機器の廃棄・売却・運搬費用
これらのコストは店舗規模や契約条件によって変動が大きいため、事前に見積もりを取っておくのが安全です。
撤退を進めるための準備ステップ
撤退は一夜にして完了するものではありません。スムーズに、かつ法的トラブルを避けながら進めるためには、段階的な準備が求められます。
- 経営状況の把握と撤退判断の明確化
- 家主や関係者との事前相談
- 撤退スケジュールの作成
- スタッフへの通知と雇用手続きの整理
- 財務・契約・設備に関する情報整理
- 閉店告知・顧客対応の準備
- 原状回復・撤去・清算業務の実行
これらの準備は同時並行で進めるケースも多く、信頼できる専門家に相談しながら進行管理を行うことで、混乱を最小限に抑えることができます。
戦略的撤退の事例【イトーヨーカドー】

首都圏に集中する戦略へ舵を切ったイトーヨーカドーは、採算が悪化した地方店舗の閉鎖を段階的に進めました。
| 年 | 対象エリア・店舗数 | 主な理由 | 主な施策 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北海道ほか 17 店 | 固定費高騰/売上減 | 事業承継先への譲渡 | 閉店損失を圧縮 |
| 2024 | 東北・信越 7 店 | 物流コスト増 | 不動産売却と賃貸転用 | 資金回収 30 億円 |
| 2025 | 地方中核都市 9 店 | 客数減少 | 従業員を首都圏へ配置換え | 人件費比率 3pt 改善 |
地域特性に合わない大型店を潔く手放し、三大都市圏へ人員と資金を集中させた結果、粗利率が回復基調に転じました。
閉店ではなく、M&Aという選択肢を

飲食店をやめる=閉店と考えがちですが、実は「譲渡」という手段で事業を手放すことも可能です。
M&A(事業売却)によって、従業員やブランド、設備などを引き継いでもらえれば、ゼロからの撤退よりもはるかにメリットが多い場合があります。
とくに近年は飲食業界のM&A市場も活性化しており、小規模店舗でも買い手が見つかるケースは増加傾向にあります。この章では、M&Aの基礎知識から進め方までを詳しく解説します。
M&Aのメリットと成功事例
M&Aを選ぶことで、単なる閉店とは異なる多くの利点が得られます。経営者にとっても従業員や顧客にとっても、前向きな形でのバトンタッチが可能になります。
- 閉店コストの回避
↳原状回復費や在庫廃棄などの支出を抑えられる - 店舗のブランドや顧客基盤を維持
↳買い手が既存の店名・コンセプトを活用する場合、認知が生きる - 従業員の雇用継続の可能性
↳スタッフが新体制でそのまま働けるケースも多い - 売却益の獲得
↳撤退による損失だけでなく、資金を得て次のステップへ
実際に、地方のカフェや居酒屋がM&Aによって法人や個人に引き継がれ、オーナーは別業態で再出発を果たしたという成功例も増えています。
M&Aを成功させるための準備と手順
M&Aは急に売り出してもうまくいくとは限りません。買い手が安心して引き継げるように、あらかじめ情報を整理しておくことが不可欠です。必要な準備事項を以下に表でまとめました。
| 準備項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 財務資料の整備 | 直近3年の売上・利益・原価などのデータ |
| 店舗設備一覧 | 厨房機器・内装備品・リース契約など |
| 従業員情報 | スタッフの人数・雇用形態・勤続年数 |
| 顧客情報・販促データ | SNSフォロワー数、会員数、販促履歴など |
| 契約関係の明確化 | 賃貸借契約、仕入れ先との契約状況 |
このような情報がそろっていれば、交渉もスムーズになり、より良い条件での譲渡が実現しやすくなります。
仲介業者の選び方と注意点
M&Aをスムーズに進めるには、適切な仲介業者の選定が非常に重要です。実績があり、業界理解のあるパートナーを選ぶことで、売却の成功率が大きく変わります。
- 飲食業界に特化した実績があるか
↳飲食特有の事情(厨房設備、賃貸契約など)に明るい業者が理想 - 成功報酬型か、着手金が必要か
↳無駄なコストを避けるには、報酬体系の確認が必要 - 店舗規模に合った支援ができるか
↳小規模店でも対応してくれる柔軟な体制かをチェック - 実名公開・匿名交渉などの選択肢
↳従業員や顧客に知られたくない場合に対応できる体制
複数社に相談・比較することで、自店に合った支援を受けられる可能性が高まります。早めの相談が、良い出会いにつながります。
おすすめ仲介業者
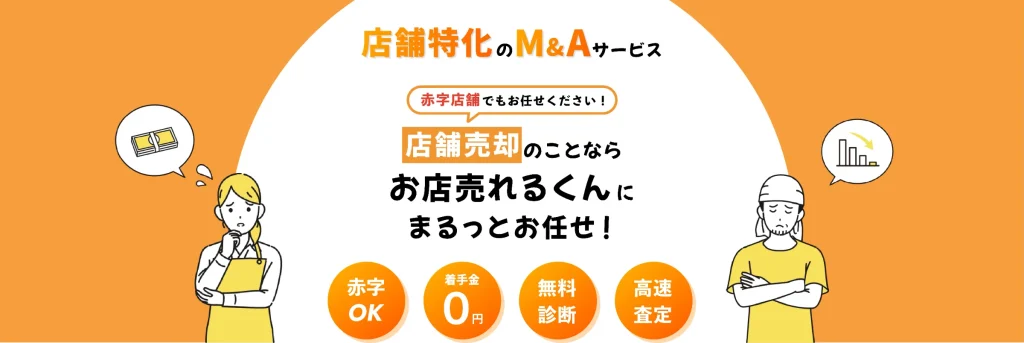
- 後継者がいない・体力的にお店を続けるのが難しい…
- 赤字経営で閉店せざるを得ないかも…廃業も視野に…
- とはいえ、「愛着ある店舗を、できるだけ高く売りたい」…
→ そんな想いに寄り添う、店舗専門のM&A仲介サービスです。お店がそこにある限り、何でも相談可能でございます。無料相談会を随時受付中になるので、是非下記よりお気軽にご連絡ください!
まとめ|戦略的撤退で未来につなぐ経営判断
飲食店経営において、「続けること」だけが正解ではありません。環境の変化や経営状況の悪化が続く中で、冷静に現実を見つめ、「撤退」という選択をすることも立派な経営判断のひとつです。
この記事では、撤退を成功に変えるための考え方、撤退判断の基準、実務的な準備、そしてM&Aという選択肢について解説しました。どの項目も、「損失を最小限にし、次に活かす」ために欠かせない視点です。
実際に撤退を進めるときには、数字の把握、関係者との調整、スタッフや顧客への誠実な対応など、多くの要素を同時に進めなければなりません。その負荷を一人で背負い込まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。