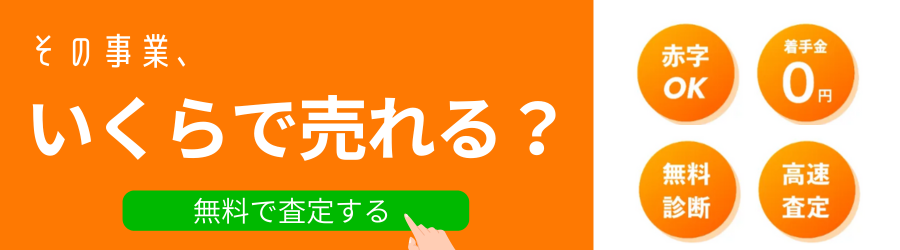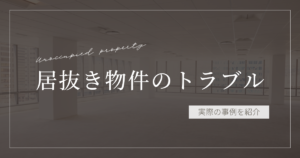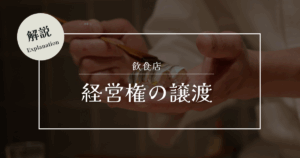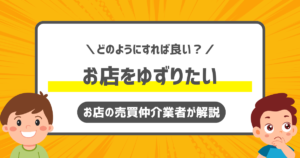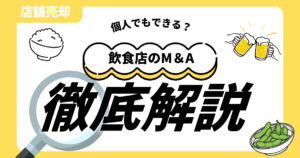飲食店を閉店する際や賃貸契約が終了するタイミングで避けて通れないのが「明け渡し」の手続きです。
しかし、この明け渡しという言葉には、似たような響きを持つ「引き渡し」との混同や、法律的な定義のあいまいさから、戸惑う方も少なくありません。
特に飲食店の場合は、原状回復の範囲が広く、什器や設備の処理、オーナーとの調整など、やるべきことが多岐にわたります。
この記事では、「明け渡し」と「引き渡し」の違いを明確にしつつ、手続きの流れや実務上の注意点、トラブルを防ぐためのポイントまでを整理して解説します。
飲食店の明け渡しと引き渡しの違い

「明け渡し」と「引き渡し」は、飲食店の退去時に頻繁に使われる言葉ですが、混同しやすいため正確な理解が求められます。それぞれが意味する内容は異なり、対応を誤るとトラブルにつながることもあります。
「明け渡し」と「引き渡し」の法律的定義
法律的には「明け渡し」と「引き渡し」は次のように定義されています。
| 用語 | 法律的な意味 | 対象 |
|---|---|---|
| 明け渡し | 物件の使用権(賃借権)を貸主へ返す行為 | 不動産(店舗など) |
| 引き渡し | 物品を相手に物理的に渡す行為 | 什器・設備などの動産 |
一方の引き渡しは、店舗内の什器や設備など「モノ」に関するやり取りです。リース契約の返却や売却なども引き渡しに該当します。
このように、対象とするものが「権利」なのか「モノ」なのかで明確に分かれるため、正しい理解と対応が必要です。

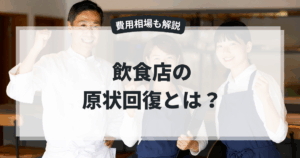
飲食店の明け渡しの流れ

店舗の明け渡しには、単なる撤収以上の準備が求められます。
段取りを誤るとトラブルや追加費用に発展する可能性もあるため、事前に必要な工程を理解し、余裕を持って準備を進めることが重要です。
契約書の確認と明け渡し条件の把握
最初に確認すべきは、現在の賃貸契約書の内容です。特に以下の点は明け渡し時の費用やトラブルに直結するため、早い段階で把握しておく必要があります。
| 確認項目 | 主なチェックポイント |
|---|---|
| 原状回復義務 | スケルトン返却か部分補修でよいかを確認 |
| 解約予告期間 | 1〜3ヶ月前通知が必要なケースが多い |
| 敷金返還条件 | 工事費控除の有無や精算方式の記載を確認 |
契約内容に不明点がある場合は、オーナーや管理会社へ早めに確認を取ることで、後々のトラブルを回避できます。
原状回復の範囲と準備内容
飲食店では火気・水・油を扱うため、原状回復の負担が大きくなりがちです。厨房や換気ダクトなど、専門業者による対応が必要な箇所もあります。
- 厨房設備の取り外し・清掃
↳油汚れの除去や給排水の処理が必要 - 天井・壁・床材の撤去
↳内装を契約当初の状態に戻す - 電気・ガス設備の撤去と安全処理
↳配線・配管の整理や閉栓処理 - 排気・排水設備の完全撤去
↳ダクトやグリストラップの撤去が義務になる場合も
内容によっては100万円を超える工事になることもあるため、必ず複数社に見積もりを依頼して比較検討しましょう。
什器・設備の撤去と廃棄
撤去すべき什器や備品の扱いは、コストにも大きく関わります。以下のような方法から適切なものを選ぶことが重要です。
| 処理方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 業者による買取 | 費用負担を軽減しつつ資金回収できる | 状態や年式によって価格が変動する |
| 産業廃棄物として処分 | 一括対応できる点で手間がかからない | 費用がかかる・分別や許可業者の確認が必要 |
| 他店舗へ移設 | 再利用による資産の有効活用が可能 | 輸送・設置の手配が必要 |
事前に何をどう処分するかリストアップし、業者と段取りを組んでおくことでスムーズに対応できます。
まとめ
飲食店の退去は、単なる引っ越しではなく、「明け渡し」という法的・実務的な手続きが伴います。
この記事では、「明け渡し」と「引き渡し」の違いを軸に、契約書の確認から原状回復、立ち会い、書類整理までの流れを詳しく解説しました。
飲食店は設備や仕様が特殊なため、退去時の工事や撤去作業も複雑になりやすく、想定以上の費用や手間がかかることがあります。今回の内容をもとに、早めの準備と情報整理を意識すれば、不要なトラブルを避けて落ち着いて行動できるはずです。