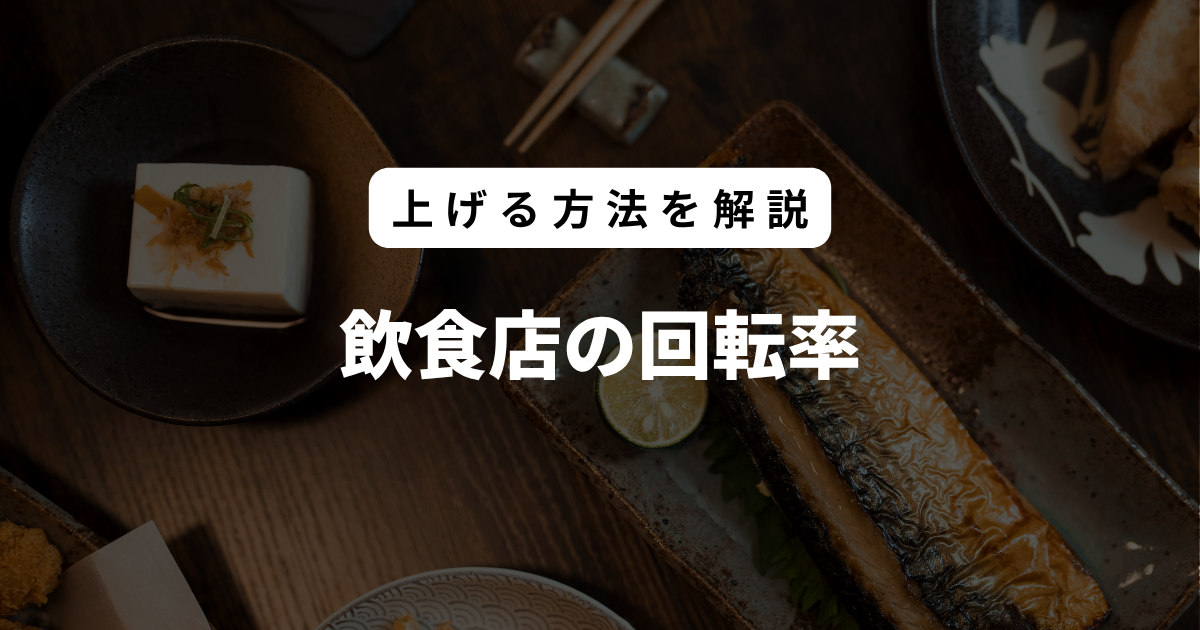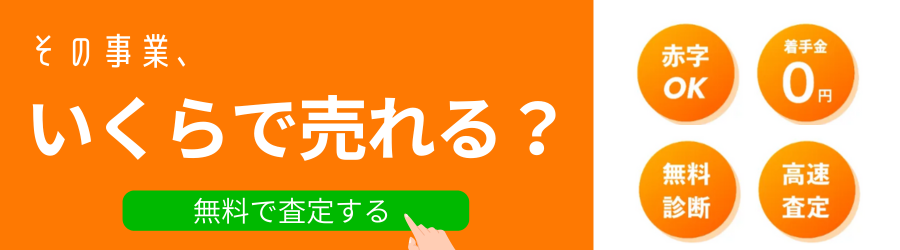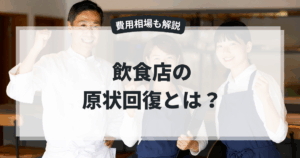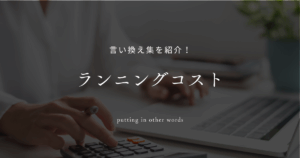「お客様が入っているのに売上が伸びない」「ピークタイムに行列ができても利益につながらない」──そんな悩みを抱える飲食店経営者は少なくありません。
その原因のひとつが“回転率”です。席数や客単価だけでなく、どれだけ効率よく席を活用できているかが、売上を大きく左右します。
この記事では、飲食店における回転率の基本的な考え方から、業態別の最適な目安をまとめました。
このページでわかること
- 飲食店における回転率の定義と計算方法
- 回転率が売上や利益に直結する理由
- 業態別に目指すべき回転率の目安
- 回転率を下げてしまう主な要因と改善策
飲食店の回転率とは?

回転率は「限られた席をどれだけ効率よく使えたか」を示す指標です。席数や客単価をいくら工夫しても、席の入れ替えが滞れば売上は頭打ちになります。
回転率の定義と計算方法
回転率には日次と時間の2通りの見方があります。目的に合わせて使い分けると分析がぶれません。
平均滞在時間の把握が重要です(例:平均45分なら、理論上は1席あたり1時間に約1.3回の入替が可能)。また、稼働率(空席時間の少なさ)とセットで見ると精度が上がります。
なぜ回転率が重要なのか?売上との関係性
売上は「客数 × 客単価」で決まります。客数は「席数 × 稼働時間 × 時間回転率」で説明できるため、回転率が上がれば客単価を変えずに売上を底上げできます。逆に、待ち時間が長くテーブルの入替が遅いと、行列があっても売上が伸びません。
| 要素 | 関係 | 改善が効くポイント |
|---|---|---|
| 客数 | 席数 × 稼働時間 × 時間回転率 | 滞在時間の短縮、空席時間の圧縮 |
| 客単価 | メニュー構成・セット率・ドリンク率 | 提供順序の工夫、追加注文の案内 |
| 回転率 | 平均滞在時間の逆数 × 稼働率 | 案内・配席・会計・片づけのリードタイム短縮 |
ポイントは、回転率を「無理に急かすこと」ではなく、「滞在に価値がない待ち時間を減らすこと」で引き上げる点です。
体験価値を保ったまま、死角時間(会計後〜次客着席まで)を削ると売上効率が上がります。
業態別・目指すべき回転率の目安
業態ごとに平均滞在時間や注文特性が異なります。下表はピーク1時間あたりの回転率と、一日あたりの目安です(席数・営業時間・商圏により変動します)。
| 業態 | 平均滞在時間 | ピーク1時間回転率の目安 | 日次回転率の目安 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ファストフード・立ち食い | 15〜30分 | 2.0〜4.0 | 5〜10 | セルフ会計と定型メニューで待ちを圧縮 |
| ラーメン・麺類 | 20〜40分 | 1.5〜3.0 | 3〜6 | 回転を左右するのは配席と会計後の片づけ速度 |
| カフェ | 45〜90分 | 0.5〜1.5 | 2〜4 | 長居対策はゾーン分けと時間帯別メニューが有効 |
| 定食・カジュアルダイニング | 40〜70分 | 1.0〜2.0 | 3〜5 | セット化と配膳導線で滞在を短縮 |
| 居酒屋 | 90〜150分 | 0.7〜1.5 | 2〜3 | ラストオーダー運用と会計分散で詰まりを回避 |
| 焼肉・ステーキ | 80〜120分 | 0.6〜1.2 | 2〜3 | 予約比率と前精算の工夫が効果的 |
自店の商圏・席構成・営業時間を踏まえ、まずは現状値を把握し、ピーク1時間の回転率を0.2〜0.3ポイントずつ引き上げるイメージで段階的に調整すると無理がありません。

飲食店の回転率のボトルネックの見つけ方

回転率を高める最短ルートは、まず現状を数字で把握することです。入店から退店までを可視化すると、時間を費やしている工程が浮かび上がり、どこから手を付けるべきかが明確になります。
時間帯別データ収集シート作成
工程ごとの時間を比較しやすいよう、1日を細かく区切って記録するシートを作成いたします。管理しやすい列見本を下表にまとめました。
| 時刻帯 | 客数 | 平均滞在分 | 平均客単価 | 合計売上 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00-11:00 | ||||
| 11:00-12:00 | ||||
| … | ||||
| 21:00-22:00 | ||||
シートはExcelやGoogleスプレッドシートで作成し、POSから出力したCSVを貼り付けると集計が容易です。1週間続ければ、曜日による傾向も読み取れます。
工程ごとの滞在時間計測方法
どの工程で時間を要しているかを測る際は、次の手順で進めてください。
- 観測対象のテーブルを3〜5卓選定し、ピーク帯とアイドル帯の両方で調査
- 入店、注文、配膳、食後、会計、退店のタイミングをストップウォッチで記録
- 2回計測したら平均を取り、工程ごとの所要時間を算出
- 合計滞在時間と全工程の合計が一致するか確認し、記録を完了
スタッフの手が離せない場合は、スマートフォンの動画を定点設置し、あとで再生速度を落として時間を測定すると正確です。
20%ルールで改善優先度を決める
得られた数字をもとに、限られたリソースで最大の効果を得るための優先度を設定いたします。
- 合計滞在時間の上位20%に該当する工程を洗い出す
↳たとえば配膳と会計の二つで全体の40%を占める場合は、この二工程を優先 - 上位工程に対し「省略できる手順」「分業できる動線」「ツールで短縮できる作業」を洗い出す
↳例:セルフレジの設置、配膳ロボットの試験導入 - 効果が見込める順に改善を実施し、翌週のデータで確認
時間帯別シートと合わせて分析することで、「ピーク時に限り会計が滞る」といった状況を把握しやすくなり、投資判断の精度が高まります。
飲食店の回転率を上げる方法3選
「お客様が入っているのに売上が伸びない」という状況の多くは、回転率を下げる要因が潜んでいます。ここでは代表的な4つの原因を取り上げ、それぞれに具体的な改善策を紹介します。
提供スピードが遅い原因と改善法
料理の提供が遅れると、客の滞在時間が長くなり回転率に直結します。原因は調理工程の複雑さや仕込み不足、注文伝達の遅れにあります。
| 原因 | 改善策 |
|---|---|
| 調理工程が多い | 人気メニューは事前仕込みで対応、調理時間の短縮を図る |
| 注文伝達の遅れ | ハンディ端末やモバイルオーダーで即時連携 |
| 仕込み不足 | ピーク前の仕込み計画をシフトごとに明文化 |
テーブルの片付け・案内が遅れる理由と対策
離席後から次客着席までの「死角時間」が長いと、稼働率が低下します。片付けと案内の連携を強化することが重要です。
- 退席が確認できた時点で即座に片付けスタッフへ連絡する
- 片付け後の卓上セッティングを標準化して短時間化する
- 案内係と片付け係の動線を近づけ、連携をスムーズにする
オペレーションの無駄を排除する方法
スタッフの動きに無駄が多いと、全体のテンポが遅れ、回転率低下につながります。業務フローを見直し、シンプルなオペレーションにすることが効果的です。
| 無駄の例 | 改善方法 |
|---|---|
| 複数回の往復で配膳 | トレー・ワゴンを使い、一度にまとめて提供 |
| 役割分担が不明確 | 接客・片付け・会計を役割ごとに明確化 |
| 客席から厨房までの距離が長い | 動線を短縮する配置換えを検討 |
まとめ|今日から始める回転率アップ戦略
本記事では、回転率の定義と業態別の目安、ボトルネックを洗い出すためのデータ収集と測定手法、即効性のある低コスト施策から中長期で効果を発揮するレイアウト・IT導入、さらに顧客体験を損なわずに自然な退店を促すアプローチまで、順を追ってご説明いたしました。
実践に移す際は、まず〈時間帯別データ収集シート〉を1週間運用し、滞在時間上位20%の工程を抽出してください。次に、卓上QR注文やセルフレジなど初期投資の小さい施策を試し、1〜2週間かけて効果を測定します。
改善幅が小さい場合は、フロアレイアウト変更やAI予約システムの導入など中長期策を検証し、ROIを比較しながら段階的に進めていただくと失敗が少なくなります。