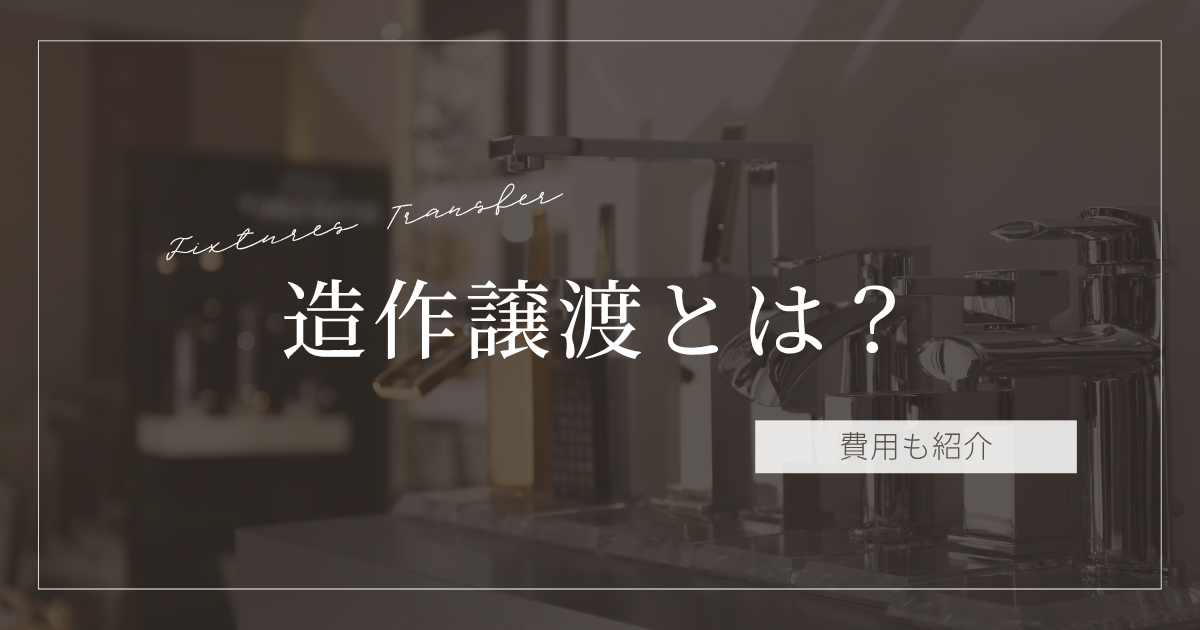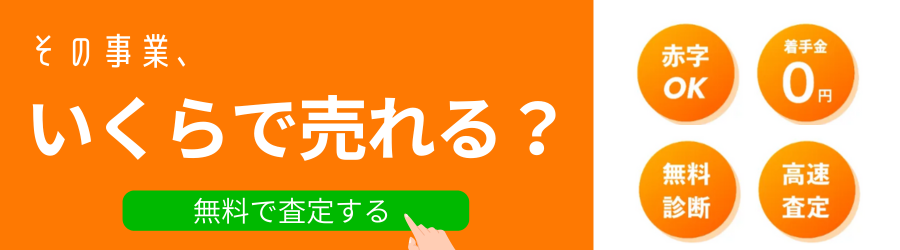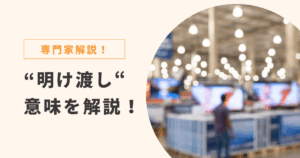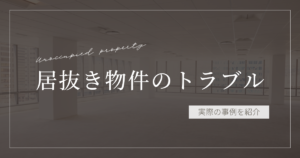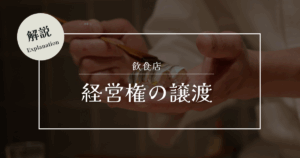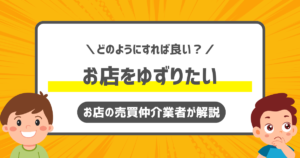店舗を開業・閉店する際に耳にする「造作譲渡」という言葉。聞いたことはあっても、「具体的に何を指すのか」「どんなときに必要なのか」と疑問を持つ人も多いでしょう。
特に飲食店や美容室などでは、内装や設備が大きなコストを占めるため、この仕組みを正しく理解することが損をしないために大切です。
この記事では、造作譲渡の定義や対象となる設備、契約の流れや注意点を体系的に解説します。
このページでわかること
- 造作譲渡の意味と対象となる設備の具体例
- 造作譲渡が行われる場面とそのメリット・デメリット
- 契約時に確認すべき手順と注意点
- よくあるトラブル事例とその防止策
造作譲渡とは

造作譲渡は、借主が自費で設置した内装や設備を、退去時に撤去せずに次の入居者に対価とともに引き渡す仕組みです。スケルトン返しと比べてコストを抑えられ、次の利用者も初期投資を減らして開業できるため、双方にメリットがある契約形態です。
造作譲渡とは何か?定義と具体例
造作譲渡は「店舗内の内装や設備を撤去せずに新しい借主に引き継ぐこと」を意味します。通常は売買契約として扱われ、賃貸借契約とは別に成立します。
譲渡価格は残存価値や使用年数、撤去にかかる費用を基準に交渉されることが一般的です。たとえば飲食店なら厨房設備や客席のカウンター、美容室ならシャンプー台や鏡が譲渡の対象になることが多くあります。

対象となる設備・内装とは
造作譲渡で引き継がれるのは、自費で設置した内装や什器・備品が中心です。一方で、リース契約や建物共有設備に含まれるものは対象外になるケースがあります。判断の目安を以下に整理します。
- 譲渡できるもの
↳厨房機器や什器、カウンター、内装工事部分など - 譲渡できないもの
↳リース契約中の機器、ビル共有の空調や電気設備 - 要確認となるもの
↳ダクトや配管など、建物の躯体と直結する部分
原状回復義務との関係
造作譲渡は原状回復義務と密接に関係します。契約で「スケルトン返し」が定められていれば撤去が原則ですが、貸主の承諾を得られれば造作を残して譲渡が可能になります。
逆に契約に明記がなくても、早めに交渉することで撤去費と譲渡金のバランスをとった合意ができるケースもあります。
| 契約条項 | 対応方針 |
|---|---|
| スケルトン返し特約あり | 撤去が原則、ただし貸主承諾で造作譲渡に切替可能 |
| 居抜き可と明記 | 譲渡対象をリスト化し、契約書に明記 |
| 条項が不明確 | 早期に貸主と協議し、撤去費と譲渡金を比較して合意形成 |
造作譲渡が行われる場面とメリット・デメリット

造作譲渡は「退去する側」と「新しく入居する側」の双方にとって、コスト削減やスピード開業といった利点があります。その一方で、契約条件や設備の状態によってはトラブルの原因にもなり得ます。
どんな場面で使われるか
造作譲渡は、特に設備投資が大きい業種で多く活用されます。以下のようなケースが典型例です。
- 飲食店の閉店・移転
↳厨房機器や内装を撤去せずに譲渡することで、退店コストを削減できる - 美容室や理容室の事業承継
↳シャンプー台や鏡、内装をそのまま活用することで買主はすぐに営業可能 - マッサージ・整体など施術系店舗
↳ベッドや間仕切りを引き継ぎ、開業準備を短縮できる
このように「初期投資の削減」と「スピード開業」が求められる場面で多く用いられています。
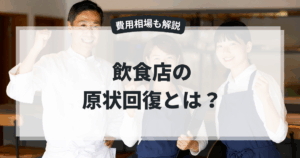
売主側のメリット・デメリット
売主にとって造作譲渡は、原状回復工事を避けながら設備を収益化できる大きな利点があります。ただし、必ずしも希望通りの価格で売却できるとは限らず、注意も必要です。
| 売主側のメリット | 売主側のデメリット |
|---|---|
| 原状回復工事を省けるため大幅なコスト削減につながる | 買主が見つからなければ撤去費用を負担する可能性がある |
| 内装・什器を対価として売却できる | 設備の老朽化が進んでいると価格がつきにくい |
| スムーズに退去できるため精神的負担を軽減できる | 契約交渉で貸主の承諾を得られない場合がある |
買主側のメリット・デメリット
買主にとっても造作譲渡は魅力的な方法ですが、設備の状態や契約条件によってリスクを負う可能性があります。メリットとデメリットを整理すると次の通りです。
- メリット
- 初期投資を抑えて開業できる/短期間で営業開始が可能/人気立地で開業チャンスを得やすい
- デメリット
- 設備が中古のため修繕費が発生するリスク/自分の希望通りのレイアウトにしにくい/契約後に不具合が見つかる可能性がある
買主は「価格の妥当性」と「設備の状態」を冷静に判断し、必要に応じて専門家に確認してもらうと安心です。
造作譲渡のトラブルを防ぐポイント
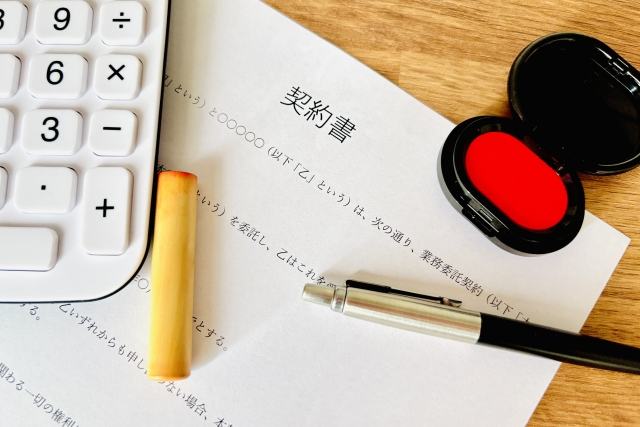
造作譲渡は便利な仕組みですが、契約内容が不明確だと後々のトラブルにつながります。特に「設備の不具合」「契約条件の認識違い」「引渡し後の対応不備」はよくある問題です。
よくあるトラブルと対策
造作譲渡の現場で起こりやすいトラブルとその対策を整理しました。
| トラブル内容 | 原因 | 防止策 |
|---|---|---|
| 譲渡対象の範囲を巡る争い | 事前のリスト化や確認不足 | 写真・リストを作成し契約書に添付 |
| 譲渡価格に対する不満 | 査定基準が不透明 | 第三者の査定を参考に妥当性を説明 |
| 瑕疵(欠陥)を巡る責任問題 | 設備チェックが不十分 | 引渡し前に稼働確認を実施し記録を残す |
こうした問題は「曖昧にせず書面に残す」ことで多く防ぐことが可能です。
契約後の設備トラブルへの備え
譲渡契約後に「冷蔵庫が壊れた」「水回りから漏水があった」といった設備トラブルが発覚することがあります。責任の所在を明確にしていないと、修繕費を巡って対立する原因になります。
- 契約書に「瑕疵担保責任の範囲」を明記する
- 動作確認のチェックリストを引渡し前に作成する
- 大きな設備は専門業者による点検を依頼する
この準備をしておけば、後から余計な費用を負担するリスクを減らせます。
引渡しから開業までの流れ
最後に、造作譲渡後のスムーズな開業に向けた流れを確認しておきましょう。引渡しから営業開始までにやるべきことをまとめると次の通りです。
| 段階 | やるべきこと |
|---|---|
| 引渡し当日 | 鍵・設備リスト・確認書類を受領し、現場で動作確認 |
| 引渡し直後 | 保健所・消防署への営業許可申請を行う |
| 開業準備 | 必要に応じた補修工事・備品の追加購入・スタッフ研修 |
| 営業開始 | オープン前告知・集客施策を実施し、開業日を迎える |
この流れを事前に把握しておくことで、造作譲渡から開業までの期間を短縮し、スムーズに事業をスタートできます。
まとめ|造作譲渡の全体像を理解し、安心して契約を進めよう
造作譲渡は、店舗の内装や設備を次の入居者に対価とともに引き渡す仕組みであり、閉店する側にも開業する側にも大きなメリットをもたらします。
本記事では、造作譲渡の定義や対象範囲、原状回復義務との関係をはじめ、活用される場面や売主・買主それぞれの利点と注意点を整理しました。さらに、契約の流れや必要な確認項目、よくあるトラブルの防止策についても具体的に解説しました。
実際に造作譲渡を行う際には、まず賃貸契約の条項を確認し、貸主の承諾を得ることが不可欠です。そのうえで譲渡対象をリスト化し、写真や状態チェックを行い、契約書に反映させることで、トラブルのリスクを大幅に減らせます。