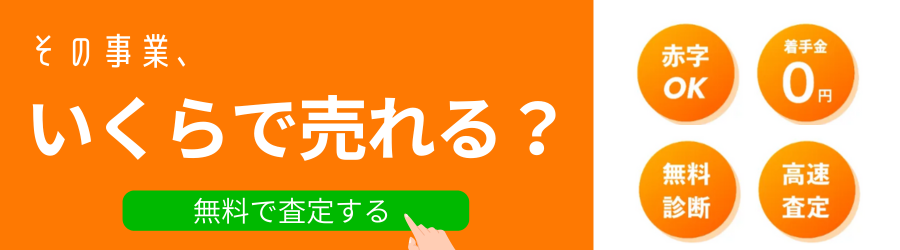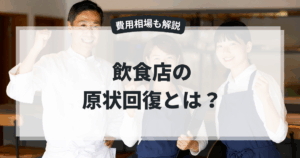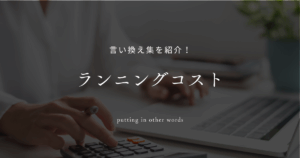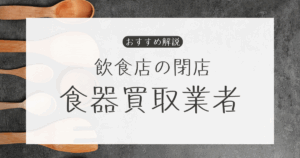飲食店経営において「資金繰りが厳しい」と感じている方は少なくありません。
売上が思うように伸びず、毎月の支払いに追われるなかで、赤字経営が続けば「もう融資なんて無理なのでは」と不安になるのも無理はないでしょう。
しかし、赤字でも融資を受けられる可能性は十分にあります。大切なのは、正しい情報をもとに行動することです。そこで本記事では、飲食店が資金繰りに悩みやすい構造的な理由から、赤字経営でも現実的に融資を受ける方法をまとめました。
このページでわかること
- 飲食店の資金繰りが悪化しやすい構造的な原因
- 赤字でも融資を受けられる条件や必要書類
- 融資を通りやすくするための実践的なポイント
- 金融機関以外の資金繰り改善策の具体例
なぜ飲食店は資金繰りが悪化しやすい?

飲食店は他の業種に比べて、資金繰りが悪化しやすいビジネスといわれています。これは経営者の力量だけでなく、業態そのものに原因があるケースも多く見られます。
固定費が高く変動費の比率が低いビジネスモデル
飲食業は、家賃や人件費といった固定費の割合が高く、経営が安定するまでに大きな負担がかかりやすい業種です。売上が上下しても、固定費は毎月変わらず発生するため、利益が出ない月が続けばすぐに資金繰りが厳しくなります。
とくに都市部の飲食店では、立地の良さを求めて高額な家賃を支払っているケースが多く、売上が想定より下回っただけで大きな赤字を抱える要因になります。また、スタッフの確保にも人件費がかかり、経営初期から大きなコストを抱える構造になりがちです。
- 家賃・共益費
↳立地に依存するため削減が難しい固定費 - 人件費
↳人手不足により賃金が高騰しやすい支出 - 水道光熱費
↳営業日数や季節による変動があるが一定額が発生 - 設備リース料・通信費
↳月々発生する継続的な支払い
現金商売なのにキャッシュフロー管理が甘くなりがち
飲食店の多くは日々の売上を現金または電子決済で受け取る「キャッシュ商売」です。これは本来、資金繰り上のメリットになるはずですが、実際には日々の仕入れや支払いに追われて「今いくら使えるのか」「今月の黒字・赤字」が把握されていないケースが目立ちます。
現金が常に手元にあることで「使ってしまいやすい」という側面もあり、帳簿や資金繰り表をつけないまま経営が進んでしまうと、気づいたときには資金ショート寸前という事態にもなりかねません。
キャッシュフローを可視化する習慣が欠かせません。
原価率・人件費率が高く、利益が残りにくい構造
飲食店は、美味しい料理やサービスを提供するために、食材費や人件費を惜しまず投入する傾向があります。その結果、売上の大部分が原価や人件費で消えてしまい、経常利益が非常に小さい構造になりがちです。
利益が残りにくい構造の例を数値で整理すると、以下のようなイメージになります。
| 費用 | 割合 |
|---|---|
| 原価(食材費) | 30% |
| 人件費 | 35% |
| 家賃・光熱費など固定費 | 15% |
| その他経費 | 10% |
| 営業利益 | 10%未満 |
このように、わずかな売上減でも赤字に転落するリスクが高く、利益を確保するには数値管理と利益構造の見直しが欠かせません。
資金繰りが悪くても飲食店が融資を受ける条件

「赤字だから融資は無理」と諦めるのは早すぎます。実際には、赤字決算であっても融資に成功している飲食店は数多く存在します。金融機関が重視するのは「これからの見通し」と「経営者の姿勢」です。
赤字でも融資が可能なケースとは?
金融機関は、単に「赤字かどうか」ではなく、「なぜ赤字になったのか」「今後黒字に戻すための方策があるか」を重視して審査を行います。
つまり、赤字決算でも説得力のある改善計画があれば、融資が認められる可能性は十分にあります。赤字でも融資が通るケースには、以下のような特徴があります。
- 一時的な要因による赤字(コロナ禍・災害など)
↳外的要因であり、事業自体の将来性があると判断される - 黒字化に向けた具体的な計画がある
↳売上向上やコスト削減策などを資料で説明できる - 自己資金や支援者の協力がある
↳資金調達の見込みが複数あることでリスクが分散される
重要なのは、過去ではなく「今後の改善余地」を証明することです。
経営計画書・資金繰り表の整え方
融資審査において最も重視されるのが「経営計画書」と「資金繰り表」です。どちらも、単なる書類ではなく、経営者のビジョンと行動力を伝える重要なツールになります。
- 現状の課題分析
↳売上低迷・コスト過多などの原因と現状把握 - 改善に向けた具体策
↳販路拡大・人件費削減・メニュー改定などの戦略 - 今後の売上・利益見通し
↳数字で示した見通しと、裏付けの根拠 - 月別の資金繰り計画
↳収支・借入・返済の流れを可視化した表
書類の説得力を高めるには、第三者のチェックを受けるのも有効です。商工会や専門家への相談を検討しましょう。
融資審査で重視されるポイントを知る
金融機関が融資を判断する際、どこに注目しているかを知っておくことで、対策が立てやすくなります。審査では「定量面」と「定性面」の両方が見られます。
融資審査における主な評価ポイントは以下のとおりです。
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| 資金使途の明確さ | 融資を何に使うかが具体的であるか |
| 返済能力 | 月々の返済が無理なくできるか |
| 経営者の熱意・姿勢 | 事業継続への覚悟や行動が伝わるか |
| 財務・数値管理能力 | 帳簿管理や資金繰りの可視化ができているか |
審査の本質は、「この事業に将来性があるか」を見極めることにあります。書類だけでなく、面談時の受け答えも評価の対象になるため、準備は入念に行いましょう。
融資を受けられる主な機関

赤字でも融資を受けたいと考える飲食店にとって、どの金融機関に相談すべきかを把握することは非常に重要です。
日本政策金融公庫:赤字でも実績あり
日本政策金融公庫(略称:公庫)は、政府が100%出資する公的金融機関で、創業や小規模事業者への融資に特化しています。赤字決算の企業に対しても、将来性があれば融資が実行されるケースが多く、飲食業界でも利用実績が豊富です。
| 制度名 | 主な内容 |
|---|---|
| 新創業融資制度 | 無担保・無保証人で最大3,000万円の融資が可能 |
| 生活衛生改善貸付 | 飲食・理美容など衛生業に特化した低利融資 |
審査においては、事業計画書の完成度が特に重視されるため、丁寧な準備が欠かせません。
信用保証協会付き融資:地元金融機関と連携
信用保証協会は、中小企業が融資を受ける際の保証人の役割を担う公的機関です。地元の金融機関と連携し、借り手が返済できなくなった場合に代位弁済を行うことで、銀行が安心して融資を実行できる体制を整えています。
この仕組みを使うメリットは以下のとおりです。
- 保証付きであるため、金融機関の審査通過率が上がる
- 各地の信用金庫・地方銀行と柔軟な関係を築ける
- 融資実行までに協会と金融機関、2つの審査が必要
保証料や条件は都道府県ごとに異なるため、詳細は最寄りの信用保証協会で確認が必要です。
商工会・商工会議所経由のマル経融資
マル経融資(正式名称:小規模事業者経営改善資金融資)は、商工会や商工会議所の経営指導を一定期間受けた小規模事業者に対して行われる無担保・無保証人の融資制度です。地域密着で信頼性が高く、赤字でも推薦を得られれば融資が受けられる可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資限度額 | 2,000万円(条件により異なる) |
| 保証・担保 | 原則不要 |
| 金利 | 低利(年1~2%台程度) |
| 利用条件 | 6か月以上の経営指導を受けること |
信頼関係を築きながら支援を受けられるため、早期の相談がおすすめです。
飲食店の資金繰りが悪くてもM&Aは可能
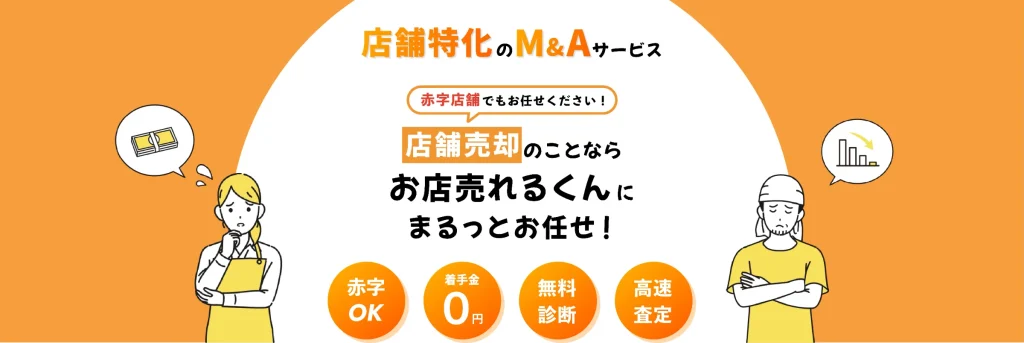
- 後継者がいない・体力的にお店を続けるのが難しい…
- 赤字経営で閉店せざるを得ないかも…廃業も視野に…
- とはいえ、「愛着ある店舗を、できるだけ高く売りたい」…
- パートナーとして、親身に寄り添って進めてほしい…
- 仲介手数料をほかの業者よりもなるべく安く抑えたい…
→ そんな想いに寄り添う、店舗専門のM&A仲介サービスです。お店がそこにある限り、何でも相談可能でございます。無料相談会を随時受付中になるので、是非下記よりお気軽にご連絡ください!
まとめ|資金繰りの立て直しは可能
飲食店は固定費の高さや利益構造の脆弱さから資金繰りに悩みやすい業態ですが、赤字だからといって融資を諦める必要はありません。重要なのは、原因を整理し、改善の見通しを具体的に示すことです。
公的機関や制度融資を活用すれば、返済負担を抑えつつ資金を確保できる道もあります。
数値管理や計画書の整備を徹底し、早めに相談機関にアプローチすることで、資金繰りの再建は十分に実現可能です。希望を持って、行動を起こしましょう。