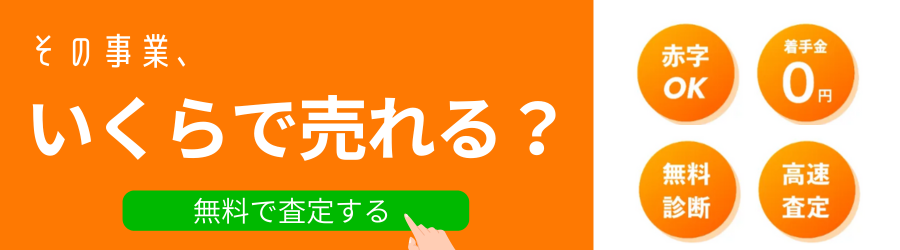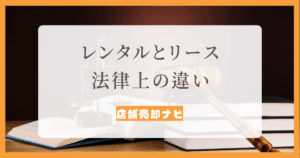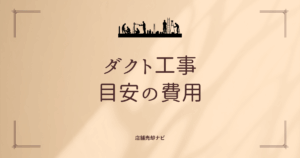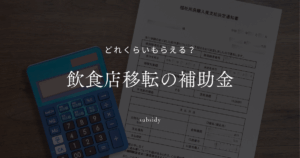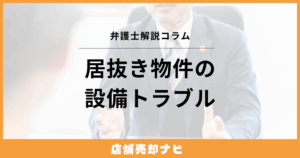「現状復帰」と「原状復帰」、どちらもよく見かける言葉ですが、意味や使い方を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。
とくにビジネスの現場では、契約書や会議資料などでこれらの言葉を使う場面が多く、誤用すれば相手に誤解を与えかねません。どちらが正しいのか分からず、不安を抱えながら文章を作成している方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、「現状復帰」と「原状復帰」の意味や違い、使い分けのポイントをわかりやすく解説します。
このページでわかること
- 「現状復帰」と「原状復帰」の意味の違い
- それぞれの正しい使用シーンと実例
- 契約書や法律文書での表現方法
- 間違いやすい理由と混同を防ぐ工夫
現状復帰と原状復帰の違い

「現状復帰」と「原状復帰」は音が似ているため混同されがちですが、それぞれ意味するところは明確に異なります。
どちらも「元に戻す」というニュアンスを持つものの、「いつの状態に戻すのか」が異なるため、使い方を間違えると誤解を招く恐れがあります。特にビジネス文書や契約書では、誤用を避けることが信頼性に直結します。
「現状復帰」とはどういう意味か
「現状復帰」は、何らかのトラブルや変化が発生した直前の状態に戻すという意味合いで使われます。ただし、正式な法律用語ではないため、厳密な場面では注意が必要です。
- 現状の意味:現在の状態や直前の状態
↳変化や問題が発生する「少し前の状態」を指すことが多い - 使用シーン:IT障害の復旧、作業ミスからの回復など
↳比較的カジュアルな会話や社内文書で使われる - 注意点:「原状復帰」と混同されやすく、正式な契約文書では使用を避けるべき
「原状復帰」とはどういう意味か
「原状復帰」は、変化が加わる前の「もとの状態」に戻すことを意味します。法的文書や契約書では、こちらの表現が正確で信頼されるものとして用いられます。
- 原状の意味:変化前・契約当初の状態
↳もともとあった状態を指す正式な表現 - 使用シーン:不動産賃貸契約の退去時、損害賠償請求など
↳法的効力を持つ書類で多用される - ポイント:「原状回復」という類語もあり、どちらも正しい

現状復帰と原状復帰の使用例

契約書や法律文書では「原状復帰」や「原状回復」が正式な表現として定着しています。一方、「現状復帰」は誤用とされる場合が多く、混同を避けることが信頼される文章を作るコツです。
契約書における正しい表現
- 「原状回復」または「原状復帰」が適切な表現
↳賃貸契約では、退去時に物件を契約当初の状態へ戻す義務を指す - 国土交通省によるガイドラインでは、
↳「原状回復」とは「借主の故意・過失などによって生じた損耗・毀損を復旧すること」と定義されている - 誤って「現状復帰」と書かれている場合は、
↳“現在の状態に戻す”という意味になってしまうため、基本的に誤りとされる
「原状回復」との関係性
| 用語 | 意味 | 使用される場面 |
|---|---|---|
| 原状回復 | 契約当初の状態に戻す義務 | 賃貸契約書、法律文書、ガイドライン |
| 原状復帰 | 建設などの現場で物件を元に戻す作業 | 工事・建設現場、オフィスや店舗の撤去工事 |
| 現状復帰 | 現在の状態に戻す意味になり誤解を招く | 契約文書では基本的に避けるべき表現 |
このように、使うべき表現は文脈によって異なります。特に契約や法律の場面では「原状回復」を選ぶことで、文章が正確かつ信頼あるものになります。
「現状復帰」の間違った使い方【会計士が解説】

「現状復帰」と「原状復帰」は、わずかな文字違いでも訴訟リスクや費用計上方法に影響します。この章では司法判断と会計実務の両面から、誤用が引き起こす具体的な不利益を整理します。
判例にみる条項無効のケース
裁判例を振り返ると、語句の選択ミスで条項が無効または無意味と判断された事例がいくつかあります。代表例を箇条書きで整理します。
- 賃貸借契約で「現状復帰」と記載した結果、入居前への回復範囲が曖昧とされ敷金返還請求を拒めなかった
- 建設請負契約で「原状復帰」とすべきところを「原状回復」としたため、元請と下請の負担割合が争点化し和解金が増額
- システム開発の和解契約書で「現状回復」を採用し、バグ修正のみが義務と判断されたことで逸失利益が回収できなかった
いずれも「該当時点を明確に示さなかった」点が無効判断の決め手となっています。文面を作成する際は、発生前か発生後かを時系列で言い切ることが必須です。
会計基準での用語使い分け
会計処理では、費用と資産の認識タイミングを誤らないためにも語句の統一が求められます。主要ガイドラインを比較すると次のようになります。
| 基準・指針 | 推奨語句 | 理由 |
|---|---|---|
| 固定資産の減価償却基準 | 原状回復 | 取得時点の状態へ戻す支出を資本的支出と区別できる |
| 収益認識基準 | 現状復帰 | サービス継続を目的とする修繕費を期間費用として扱う |
| 工事契約会計指針 | 原状復帰 | 契約解除時に完成前原価を戻す場面で用いる |
基準名や注解の原文に合わせることで、監査人との認識ずれを防げます。また、社内科目コードに語句を対応付けておくと仕訳時の入力ミスを減らせます。
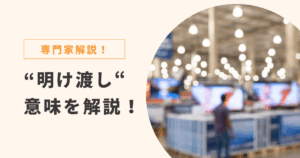
まとめ
この記事では、「現状復帰」と「原状復帰」の違いを中心に、意味や使い方、ビジネスでの適切な表現について解説しました。
「現状復帰」は日常会話で使われることがあるものの、契約書や法律文書では誤用とされるケースが多く、避けるべき表現です。
一方、「原状復帰」や「原状回復」は、もともとの状態に戻すことを意味し、法的にも正確で信頼される表現です。
実際の業務では、使用する場面や文脈をよく見極めた上で言葉を選ぶことが求められるでしょう。