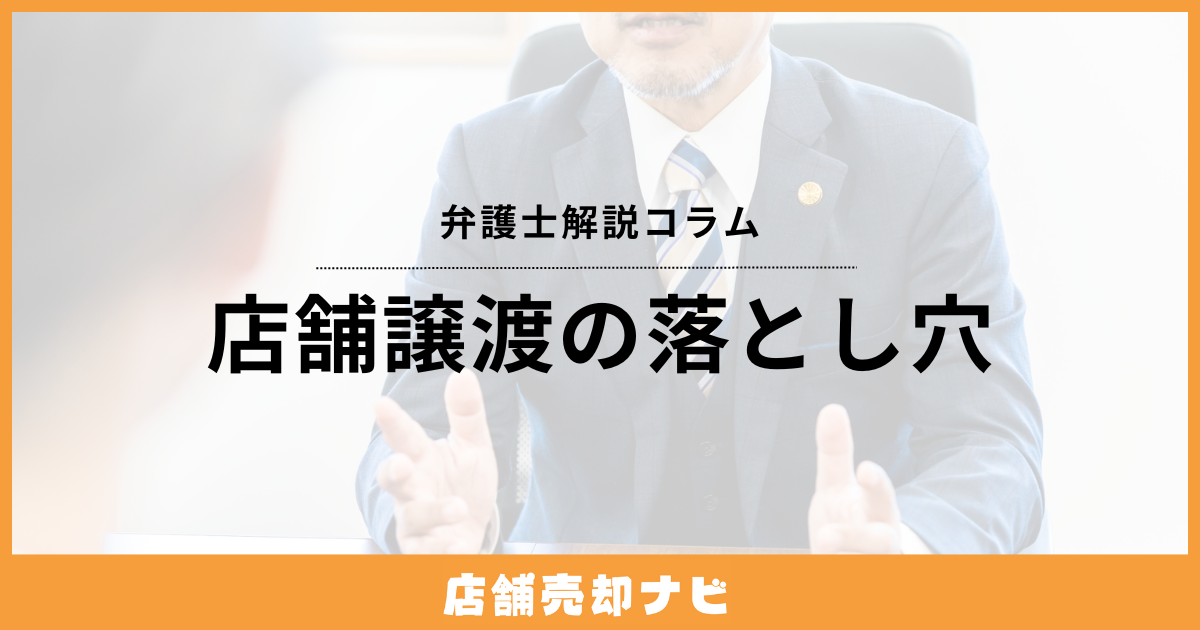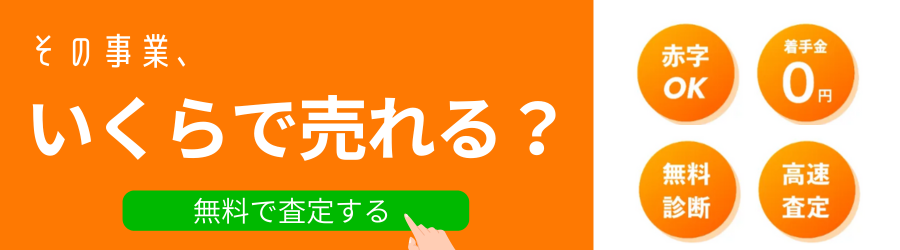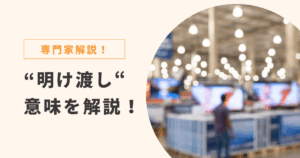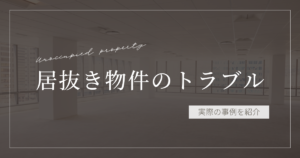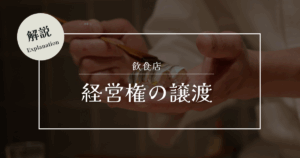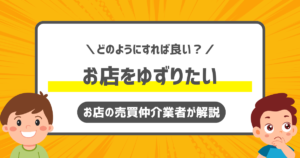飲食店の譲渡には“業種特有”の法的リスクがある!
飲食店の店舗譲渡は、設備や内装が高額である分、譲渡価格も比較的高めに設定されます。特に居抜き譲渡では、ダクトや厨房機器などが一体として取引されるため、譲渡が成立すれば売主・買主ともにメリットが大きい一方で、飲食業に特有の法的・行政的・近隣トラブルが発生しやすい点に注意が必要です。
店舗譲渡の落とし穴①:ダクトの「所有権」と「使用許諾」
建物全体に接続している排気ダクトのうち、専有部分を超える部分(例えば共用部を通る立ち上げダクト等)については、実は売主が自由に譲渡・使用させることができないケースがあります。
【実例】ビルオーナーの承諾なく共用部ダクトの一部を譲渡対象に含めて契約 → 引渡後に新テナントが使用を制限され、損害賠償請求。
→ ダクトの使用許諾契約の有無や、共用部設置の占有・改修に関する貸主承諾の有無は、必ず事前確認・書面化が必要です。
店舗譲渡の落とし穴②:グリーストラップの清掃・容量トラブル
グリーストラップは衛生管理上必須ですが、清掃義務が果たされていないまま譲渡されるケースが少なくありません。さらに、買主が想定する調理規模に対し、容量が足りないことも。
【実例】譲渡契約書には“現状有姿”と記載されていたが、引渡後の保健所立入検査で「清掃不良・悪臭」で営業停止命令 → 契約解除請求へ。
→ 現状有姿でも、重要な衛生設備は“使用に適した状態か”をチェックリスト化し、共有・記録することが重要です。
店舗譲渡の落とし穴③:保健所の「営業許可」更新と事業主体の変更
保健所の営業許可は事業者(法人・個人)に紐づくものであり、居抜きで引き継いだ設備であっても、買主が改めて申請・許可取得を行う必要があります。
【実例】譲渡契約締結直後に営業開始を予定していたが、内装変更箇所が軽微であっても“構造設備の確認”が必要とされ、2週間開業が遅延 → 損害賠償請求。
→ 譲渡対象の営業許可が“そのまま使える”と思い込まず、買主側の申請スケジュールも見越して契約日・引渡日を設計する必要があります。
店舗譲渡の落とし穴④:臭気・排気に関する近隣トラブル
厨房の排気が上階住戸や周囲のテナントに影響を及ぼす場合、営業開始後に苦情が寄せられ、貸主から“使用停止”を求められる事態もあります。
【実例】譲渡契約時に臭気の強い業態(焼肉)での転用が予定されていたが、上階テナントからクレーム → 貸主が契約解除通告。
→ 契約書に“貸主による承諾取得を条件とする”条項や、近隣苦情発生時の対処に関する合意条項が必要です。
店舗譲渡の落とし穴⑤:隣接事業者・商店会との“暗黙の了解”
個人経営の飲食店では、地元商店会や隣接店との非公式な“了解”に基づいて、看板設置・路上看板・出入口共有などがなされていることがあります。
【実例】出入口の共有をしていた隣接店舗が、買主に変更されたことに不満を抱いてトラブル化 → 商店会を巻き込んで営業妨害的対応。
→ こうした非明文化の利用関係は、必ず売主側に「黙示的な利用ルール」「地元関係の事前挨拶」などを確認し、事前に合意の上で譲渡を進めることが必要です。
藤間崇史弁護士のワンポイントアドバイス

飲食店は、物件構造・営業許可・近隣関係といった“見えないリスク”を多く内包しています。
契約書上「現状有姿」「一切免責」と記載しても、法的には隠れた契約不適合や説明義務違反が成立する場合があり、譲渡代金の返還や損害賠償責任が発生することも。
譲渡契約を進める際には、売主・買主だけでなく、仲介者も交えた“三者チェックリスト”方式で、トラブルの芽を潰す契約設計と説明が不可欠です。
まとめ:飲食店の譲渡は「法律」「設備」「地域感覚」の三位一体で
飲食店の店舗譲渡は、収益性が高い一方で、専門的なリスクが多層的に絡み合っています。
契約書の整備、事前調査、地域調整という三つの視点から、慎重かつ戦略的に譲渡を進めることが、トラブルのない店舗売却成功への近道となります。