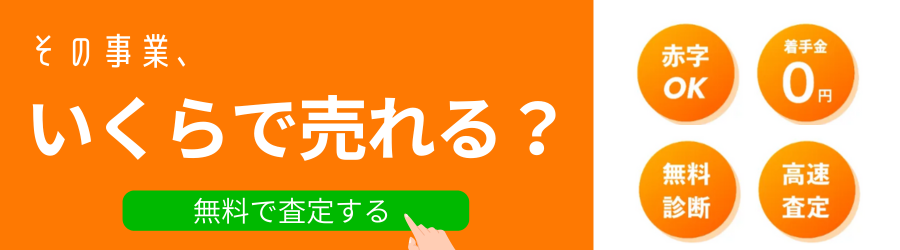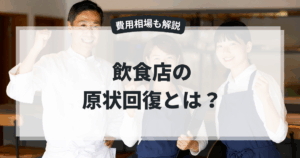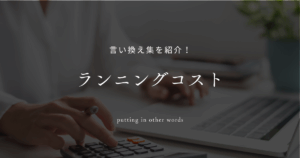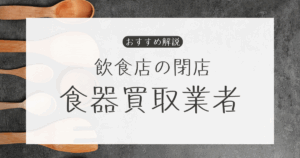経営を続けるなかで、「そろそろ店を手放そうか」と考えるタイミングは誰にでも訪れるものです。そのとき多くの人が直面するのが、「譲渡」と「売買」、どちらを選ぶべきかという疑問です。
一見すると似たような言葉ですが、実は法的な位置づけや手続きの流れ、そして何よりその背景にある“意味合い”が大きく異なります。
この違いを理解せずに選択をしてしまうと、損失を被ったり、思わぬトラブルに巻き込まれたりすることもあります。そこで本記事では、譲渡と売買それぞれの特徴を分かりやすくまとめました。
このページでわかること
- 「譲渡」と「売買」の定義や意味合いの違い
- 契約手続きや法的対応の違い
- 金銭面・信頼関係など状況に応じた判断軸
- 譲渡・売買を選ぶべき具体的なケース
- 手続きに必要な準備と専門家の活用法
譲渡と売買の違いとは?

飲食店を手放す際には、「譲渡」と「売買」という二つの方法がよく使われます。
どちらも店舗の経営権を他者に引き渡す点では共通していますが、その内容や背景には明確な違いがあります。単なる言葉の違いに見えても、選ぶ手法によって今後の人間関係や金銭面、法的責任まで大きく変わるため、正確な理解が欠かせません。
「譲渡」は、感情や信頼関係を前提にした引き継ぎが多く見られ、必ずしも金銭を伴わない場合もあります。一方の「売買」は、契約書を交わし、金銭と店舗資産などを交換する明確な商取引です。
| 比較項目 | 売買 |
|---|---|
| 契約の性質 | 金銭対価による商取引 |
| 価格の決定 | 資産評価や営業権に基づく |
| 契約書 | 売買契約書(詳細な明記) |
| 税務対応 | 課税処理が必須 |
| 目的 | 利益確保・事業価値の現金化 |
「譲渡」とは?
譲渡とは、営業権や設備、店舗の運営権を他者に引き渡す行為を指します。特徴的なのは、必ずしも金銭のやりとりが前提ではなく、信頼関係や事情に基づく「引き継ぎ」の側面が強い点です。
たとえば、親が子に、または師匠が弟子に店を譲るようなケースでは、形式的には譲渡契約書を交わすこともありますが、その背後には人間関係が大きく関係しています。
金額も実勢価格ではなく、象徴的な「名義変更料」のような扱いになることも珍しくありません。
「売買」とは?
売買は、飲食店という事業を資産とみなし、金銭と引き換えに契約を交わす「商取引」の一形態です。ここでは人間関係や信頼よりも、市場価格や資産評価に基づいた合理的な判断が重視されます。
売買契約では、店舗の設備・什器、在庫、営業権、賃貸契約の地位などが明確にリストアップされ、価格交渉が行われます。
買い手はその内容をもとに事業としての価値を見極め、支払い金額を決定します。売り手にとっては、利益の確保や損益処理の観点からも重要な手続きとなります。
法律・契約上の違い
譲渡と売買は、法律や契約、税務の面でもいくつかの違いがあります。契約時にどのような書類を準備すべきか、どの税金が発生するか、どこまで権利義務を移すかといった点で明確に分かれています。
- 契約の形式が異なる
↳譲渡は「営業譲渡契約」、売買は「売買契約書」 - 対象範囲の明確さに差がある
↳売買は資産・負債を個別に明記、譲渡は包括的に扱うことが多い - 税務の取り扱いが異なる
↳売買は消費税・所得税などの課税対象、譲渡は条件により非課税となるケースも - 責任の所在に注意が必要
↳譲渡では信頼関係による部分が大きく、後のトラブルになりやすい
譲渡・売買どちらを選ぶ場合でも、契約内容は将来のトラブル回避に直結します。書面に何をどう残すか、税務処理をどう進めるかなど、事前準備と専門家の意見が非常に重要です。

譲渡・売買の実務手続きの違い

飲食店を譲渡・売買するときには、さまざまな法的・実務的ステップや書類が必要になります。
譲渡契約の手順と必要書類(造作譲渡・事業譲渡含む)
譲渡には「造作譲渡契約」や「事業譲渡契約」といった形態があります。
これらを円滑かつトラブルなく進めるには、契約書の作成と必要書類の整備が不可欠です。
- 事業譲渡契約書の作成
↳譲渡対象・譲渡金額・引き渡し条件・競業避止義務などを明記する契約書が必要です。 - 設備・資産の明細書
↳厨房機器・内装・什器など、譲渡対象を詳細にリスト化して記録します。 - 本人確認書類や営業許可証などの基本書類
↳売り手・買い手双方に必要で、信頼性を担保するために重要です。
売買契約の進め方と注意点(居抜き売却、M&Aなど含む)
売買は、店舗やその営業権を明確な対価で移転する手続きです。
特にM&Aなどを検討する場合は、精密な進行と準備が必要になります。
| ステップ | ポイント |
|---|---|
| 許認可の扱い | 事業譲渡では再取得が必要。株式譲渡では引き継ぎが可能です。 |
| 契約書の精度 | 資産・負債・従業員・許認可などを明記し、条件を明確化します。 |
| 交渉と条件整理 | 仲介会社や専門家のサポートで、条件調整をスムーズに行います。 |
賃貸契約・従業員・設備の扱い方
譲渡・売買では、賃貸物件・従業員・設備の取り扱いも重要です。
これらをどう整理し、契約に明記するかによって、トラブルの有無が左右されます。
- 賃貸契約の引き継ぎ
↳新オーナーとの契約をスムーズに行うため、貸主の承諾が必要な場合があります。 - 従業員の雇用継続
↳雇用条件を明記し、継続雇用か退職かを明確にしておく必要があります。 - 設備の引き渡し条件
↳状態や譲渡範囲を契約に記載し、現状有姿での取り扱いかどうかを合意しておきます。
まとめ
飲食店の譲渡と売買は、どちらも店舗の引き継ぎを意味しますが、その性質や手続き、背景にある考え方は大きく異なります。
譲渡は信頼関係や感情的な要素を含む引き継ぎであり、売買は明確な対価と契約に基づく商取引です。
自身の目的が「誰かに引き継いでほしい」のか、「金銭的な成果を得たい」のかによって、最適な手法は変わります。
また、どちらを選ぶ場合でも、契約書の作成や法的な手続き、税務面の確認が必要になります。