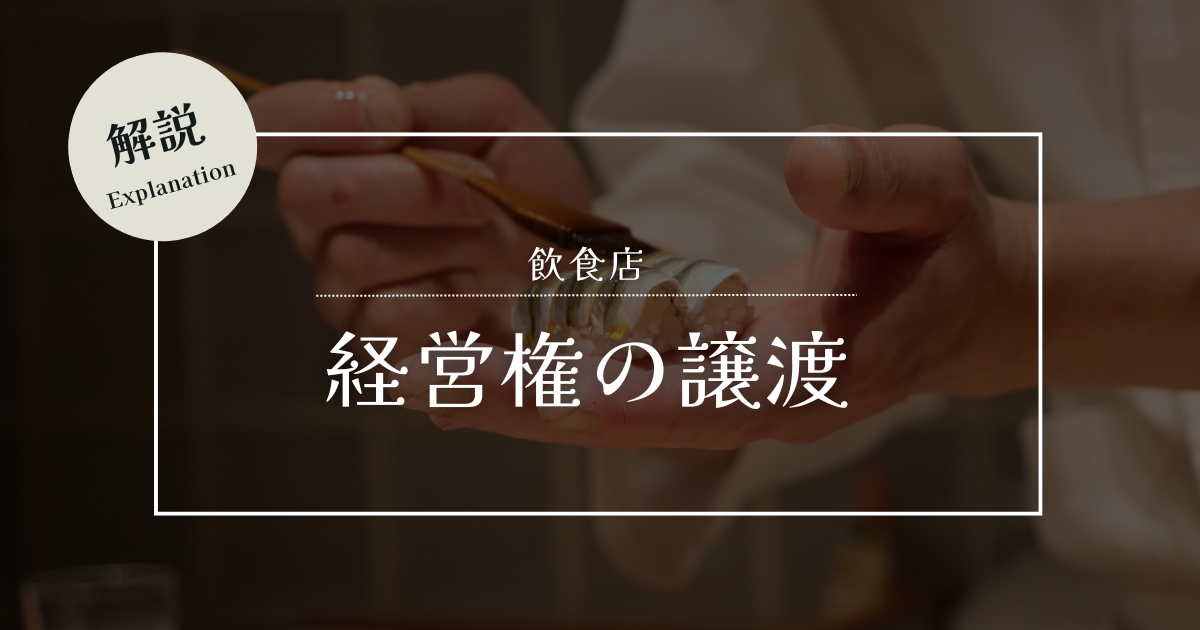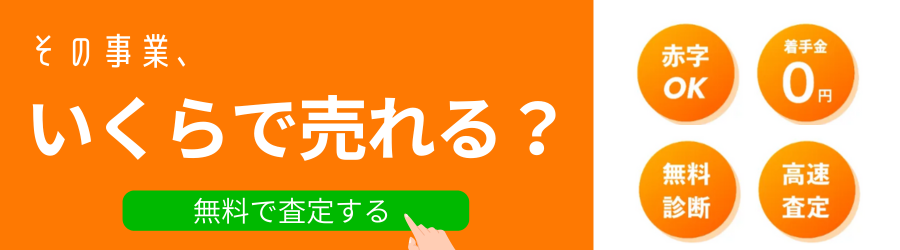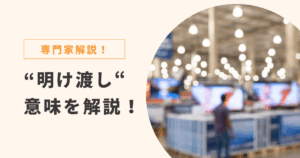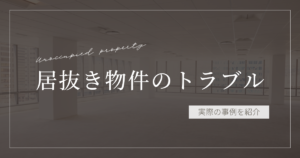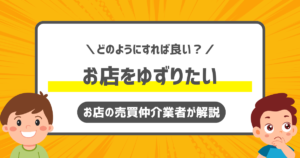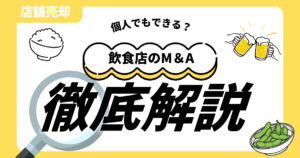飲食店の経営から撤退したい、あるいはこれから新たに店舗を引き継ぎたい。そんなタイミングで必要になるのが「経営権の譲渡」に関する正しい知識と準備です。
しかし、法律や契約、設備の引継ぎなど、検討すべきことは意外に多く、どこから手をつけてよいかわからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、飲食店の経営権譲渡に必要な手順や書類、契約書の作り方、相場の考え方、トラブル回避の方法まで、実務に役立つ情報を網羅的にまとめました。
このページでわかること
- 飲食店の経営権譲渡の基本知識と営業譲渡との違い
- 経営権を譲渡・譲受するための具体的な流れと必要書類
- 契約書テンプレートの活用方法と注意すべき条項
- 譲渡時の相場と価格設定の判断ポイント
飲食店の経営権の譲渡方法

飲食店の経営権を譲渡するには、単なる売買契約にとどまらず、物件や設備、スタッフ、行政手続きに至るまで多岐にわたる準備が必要です。しかも、これらを適切な順序で進めなければ、思わぬトラブルを招くこともあります。
契約書作成と必要な条項
経営権の譲渡契約は、後々のトラブル防止に直結する最重要書類です。内容が曖昧だったり、抜けがあったりすると、譲渡後に想定外の問題が発生しかねません。
契約書には以下のような内容を盛り込んでおくと、安全性が高まります。
- 譲渡対象の範囲と引渡し期日
↳曖昧にせず、数量・状態も明記 - 売買金額と支払い条件
↳分割払いや手付金の有無も記載 - 許認可の移管責任
↳どちらが主導で手続きを行うか - 従業員の雇用継続方針
↳再雇用の条件や契約形態 - 競業避止・秘密保持条項
↳退職後の出店制限など
契約書はテンプレートを使ってもよいですが、自店の実情にあわせたカスタマイズが不可欠です。行政書士や弁護士によるチェックも推奨されます。
行政への届け出・許認可変更手続き
経営者が変わるだけでは、営業許可などの名義は自動で移りません。
管轄行政への届け出を怠ると、営業停止になるリスクすらあるため、慎重に進める必要があります。以下は、主な行政手続きと対応先の一覧です。
| 手続き内容 | 提出先 |
|---|---|
| 営業許可の名義変更 | 管轄の保健所 |
| 防火管理者の変更届 | 地域の消防署 |
| 事業主変更届 | 税務署 |
| 労災・雇用保険の事業主変更 | 労働基準監督署・ハローワーク |
| 年金・社会保険の事業所変更 | 年金事務所 |
これらは自治体や営業形態により異なる場合があるため、各機関に事前相談しておくと安心です。
不動産・設備・デジタル資産の引継ぎ方法
譲渡時の混乱を防ぐには、実際の引渡し段階で「何を・いつ・どうやって」受け渡すかを明確に決めておくことが不可欠です。
- 店舗の鍵と賃貸契約書の引渡し
↳オーナーの立ち会いを求めることも多い - 厨房設備や什器の動作確認
↳引渡し当日の確認リストが有効 - POS・会計ソフトの設定確認
↳マニュアル共有や再設定が必要になるケースも - SNSやレビューサイトの管理権限移管
↳管理者メールアドレスの変更が基本
重要なのは、これらを曖昧にせず「引渡し書」などに明記すること。あとで「聞いてない」とならないよう、書面ベースの対応が原則です。
従業員や顧客への告知と対応
経営権譲渡は、内部スタッフや顧客にとっても重大な変化です。安心して継続利用・勤務してもらうには、適切なタイミングと内容で告知を行うことが重要です。
従業員・顧客それぞれへの対応方法を表にまとめました。
| 対象 | 対応内容 |
|---|---|
| 従業員 | 面談形式で経緯を説明し、契約条件変更がある場合は書面で同意取得 |
| 顧客 | 店頭ポスターやSNSでのお知らせ。営業時間・ブランド変更時は事前案内を徹底 |
こうした事前の丁寧なコミュニケーションは、移行後の集客やスタッフ定着にも大きく影響します。
飲食店経営権の譲渡相場

経営権の譲渡において、「いくらで売るか」「いくらで買うか」は最大の関心事です。しかし、その価格には明確な相場表が存在するわけではなく、店舗の条件や立地、営業状況などによって大きく変動します。
ここでは、地域や業態別の傾向、評価基準、適正価格を見極めるための実践的な考え方を整理します。
地域別・業態別の相場の目安
飲食店の経営権譲渡価格は、立地や業態によって大きく異なります。特に都市部と地方では、坪単価に数倍の差が出るケースもあります。以下に、地域と業態ごとの相場傾向をまとめました。
| 地域 | 業態 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 都心部(東京・大阪など) | カフェ・バル | 15〜30万円 | 内装やデザインの評価が価格に大きく影響 |
| 地方都市 | ラーメン・定食系 | 5〜15万円 | 設備状態と固定客の有無が重視される |
| 観光地 | スイーツ・テイクアウト専門 | 10〜25万円 | 立地の回転率が評価基準に反映 |
| 住宅地 | ファミリー向けレストラン | 8〜18万円 | 近隣住民からの評判と駐車場の有無が影響 |
このように、相場は一概に決まっておらず、複数の要因が絡み合っています。周辺の事例や不動産業者の情報を参考に、実情に近い価格帯を把握しましょう。
相場を決める主な評価ポイント
経営権譲渡の価格は、「店舗の魅力」だけで決まるわけではありません。買い手が価値を感じるポイントがどこにあるかを客観的に整理することが重要です。
- 立地条件
↳人通り・駅からの距離・駐車場の有無などが評価の基準に - 店舗の状態と設備
↳厨房設備のグレードや内装の新しさが価格に直結 - 営業実績や黒字化状況
↳直近の売上や営業年数が信頼性につながる - 契約条件(賃料・保証金など)
↳割安な家賃や好条件の契約は付加価値として評価 - ブランド力やSNS・レビュー評価
↳口コミ評価の高い店舗は買い手にとって魅力的
これらを総合的に見て価格を設定することが、納得感のある交渉につながります。
譲渡価格を適正に設定するためのチェックリスト
価格設定で失敗しないためには、感情ではなく「事実ベースのチェック」が欠かせません。高すぎても売れず、安すぎても損をするため、冷静な判断が求められます。
以下は、譲渡価格を検討する際に確認すべきチェック項目の一例です。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 賃貸条件 | 賃料・共益費・敷金礼金などのバランス |
| 設備状況 | 厨房機器の年式・動作状況・修理履歴 |
| 売上実績 | 月商・営業利益・固定客の有無 |
| 競合の状況 | 近隣エリアの競合店数・特徴 |
| 運営の引継ぎやすさ | 従業員の継続雇用可否・マニュアル整備 |
これらの情報を整理した上で、必要であれば第三者(専門家)の意見を仰ぐのも一つの方法です。適正価格を導くには、主観に頼らず、論理的な裏付けを持つことがカギになります。
飲食店経営権の契約書テンプレート
経営権譲渡における契約書は、譲渡内容や条件を明文化し、トラブルを防止するための中心的な書類です。しかし、ゼロから作るのは難しく、時間もかかります。そこで役立つのがテンプレートの活用です。ただし、そのまま使うのではなく、必ず自店舗の事情にあわせたカスタマイズが求められます。

経営権譲渡契約書に必須の条項とは
契約書のテンプレートを使用する際でも、抜け落ちてはならない重要な条項があります。どれもトラブル回避のために欠かせない要素であり、曖昧な表現を避ける必要があります。
- 譲渡対象の範囲と明細
↳店舗・設備・許認可・デジタル資産などを具体的に記載 - 譲渡価格と支払い方法
↳一括か分割か、支払い期日の明確化 - 引渡し日と営業権移転のタイミング
↳期日の確定がトラブル防止につながる - 名義変更・行政手続きの責任分担
↳誰がどこまで対応するかを明記 - 競業避止・秘密保持条項
↳退職後・譲渡後の活動制限の範囲を定義
契約内容の文言はできるだけ明確に記載し、読み手によって解釈が分かれないようにすることが重要です。
>>テンプレートはこちら
契約書テンプレートのダウンロードと活用方法
テンプレートを活用することで、契約書作成の手間を大きく省略できます。ただし、信頼性のある出典からダウンロードすることが前提です。
以下に、主な活用方法を表にまとめました。
| 活用ポイント | 説明 |
|---|---|
| 条項の全体構成を把握する | 書き出しから締結条項までの流れを確認し、構成を理解 |
| 自店舗に不要な項目を削除 | 従業員引継ぎやデジタル資産がない場合はその条文を削除 |
| 補足条項を追加 | レビューサイト対策や顧客情報の扱いなど、必要に応じて加筆 |
| 専門家に最終チェックを依頼 | 文言の不備や法的リスクをチェックしてもらう |
テンプレートをそのまま使うのではなく、「土台」として捉え、自分の店舗用に整えていくという姿勢が大切です。
まとめ
飲食店の経営権譲渡は、単なる売買ではなく、店舗の資産や信用、運営体制ごと引き継ぐ大きなプロセスです。
正しい手順を踏み、契約書や行政手続きを丁寧に進めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、価格設定や交渉、従業員や顧客対応など、実務的な配慮も欠かせません。
テンプレートや専門家の力を活用しながら、自店に合った形で進めることが大切です。