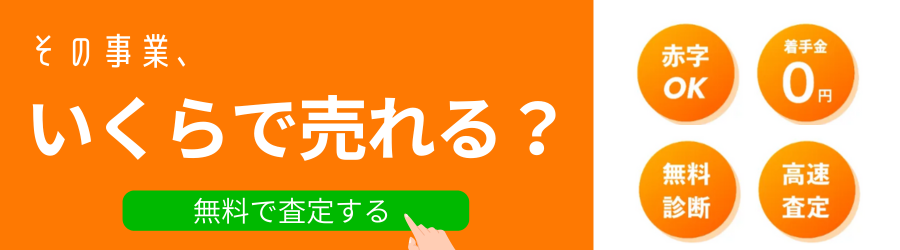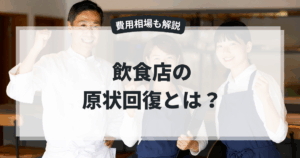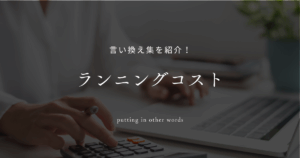飲食店を経営している、または開業を目指している人にとって「原価率」は避けて通れない数字です。
しかし「どのくらいが普通なのか」「自分の店の原価率は適正なのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、業態別や商品ジャンル別に平均原価率の目安を一覧で整理し、利益を確保するために押さえるべきポイントまで丁寧に解説します。
このページでわかること
- 居酒屋、カフェ、ラーメン店など業態別の平均原価率がわかる
- フード、ドリンク、デザートなど商品ジャンルごとの原価率の違いが整理されている
- 原価率の正しい計算方法と注意点が理解できる
- 原価率を下げるための具体的な施策とメニュー戦略が学べる
原価率の計算方法

原価率は、単なる経営指標ではなく、店舗の利益構造を左右する重要な概念です。正しい理解を持つことで、数字に振り回されずに戦略的な意思決定が可能になります。
原価率の計算式と注意点
原価率とは、売上に対して食材費が占める割合を示す指標です。基本的な計算式は以下の通りです。
原価率(%)=(食材費 ÷ 売上)× 100
例えば、食材費300円の料理を1,000円で販売すれば、原価率は30%となります。
ここで注意したいのは、ロスや仕入れミス、返品などの影響を考慮する必要があるという点です。
FLコスト
原価率が低くても利益が出ないこともあれば、高くても黒字経営を維持している店舗もあります。その違いを理解するためには、「利益率」や「FLコスト」との関係を把握する必要があります。
- 利益率=(売上 − 食材費 − 人件費)÷ 売上 × 100
↳店舗に実際に残る利益を示す指標 - FLコスト=原価率 + 人件費率
↳55〜65%以内が理想的とされる
つまり、原価率単体で見るのではなく、人件費を含めた全体のバランスを見ることが健全な経営には不可欠です。
【業態別】飲食店の平均原価率一覧

| 業態 | 平均原価率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 居酒屋 | 30〜40% | 刺身など高原価商品が多い アルコールで低原価バランスを調整 |
| カフェ 喫茶店 | 24〜35% | ドリンク中心なら原価率は低め コーヒー原価10%前後 |
| ラーメン店 | 25〜30% | スープや具材で原価に差が出る 個人店とチェーンで差あり |
| 焼肉店 | 30〜40% | 高級志向は原価が高い 肉の質によってばらつきあり |
| ファストフード テイクアウト | 25〜30% | 提供スピード重視 大量仕入れで原価圧縮可能 |
飲食店の業態ごとにどれくらいの原価率が一般的かを理解することは、適正な価格戦略やメニュー構成を考える上で不可欠です。
居酒屋の原価率と特徴
居酒屋の平均原価率は30〜40%とやや高めです。特に魚介類を中心とした店舗では刺身などの高原価商品が多く、40%を超える場合も珍しくありません。
一方で、アルコール類は原価率10〜15%と低いため、これらを組み合わせて全体のバランスを取る必要があります。
回転率の高い業態ではあるものの、価格帯の幅が広いため、利益を確保するにはメニュー構成の工夫が求められます。
カフェ・喫茶店の原価率
カフェや喫茶店の原価率は24〜35%程度で、特にドリンク中心の営業形態であれば20%台に抑えることも可能です。コーヒー1杯あたりの原価は10%前後と低く、安定した利益を出しやすい業態です。
ただし、客単価が低く回転率もそれほど高くないため、席数やオペレーション効率によって収益性が左右されやすい点に注意が必要です。
ラーメン店の原価率
ラーメン店の原価率は個人店で30%前後、チェーン店では25%程度といわれています。
ラーメン1杯あたりの原価は、スープ、麺、具材を含めておおよそ200〜300円が目安で、販売価格に対して30%前後になることが多いです。自家製スープや麺を使用する場合は原価が上がる傾向がありますが、その分、味や品質に差別化を出しやすい利点もあります。
焼肉店の原価率
焼肉店の原価率は平均30〜40%で、特に高級志向の店舗では40%を超えることもあります。肉の品質にこだわる分、食材原価が高くなるため、客単価も高く設定される傾向です。
逆に食べ放題業態では30%程度に抑えつつ、ドリンクや追加オーダーで収益を確保するスタイルが多く見られます。仕入れ先との関係や在庫管理の巧拙が、利益に直結しやすい業態です。
ファストフード・テイクアウト業態の原価率
ファストフードやテイクアウト業態では、原価率は25〜30%程度が目安です。短時間で大量に提供できる分、仕入れやオペレーションの最適化がしやすく、利益構造を作りやすい特徴があります。
ただし、包装資材や配達手数料がかかる場合、見かけの原価率以上にコストがかさむこともあり、原価管理の視点では細かなコスト項目の把握が重要となります。
飲食店の原価率ランキング

| ジャンル | 平均原価率 | 特徴 |
|---|---|---|
| フード (主食・一品料理) | 28〜40% | 魚介や肉を使うと高原価に ボリューム感・満足度重視の傾向 |
| ドリンク (アルコール・ソフトドリンク) | 5〜30% | ソフトドリンクは原価率最小 アルコールでも割材系は低原価 |
| デザート | 40〜55% | 見た目重視・高品質素材で高原価 SNS映えを狙いやすい |
今回は、原価率が高いジャンルを1位として掲載しております。

1位:デザートの原価率
ケーキやアイス、フルーツを使ったデザート類は原価率が高くなる傾向があります。
平均して40〜55%ほどで、見た目や素材にこだわるとさらに高くなります。
手間と時間もかかるため、粗利は低くなりがちです。ただし、満足度やSNS映えを狙った集客要素としては強力な武器になるため、戦略的に扱うことが重要です。
2位:フード(主食・一品料理)の原価率
主食や一品料理など、いわゆる「食事系」のフードは、原価率が比較的高くなりがちです。
平均では28〜40%ほどで、メニューによっては50%を超えることもあります。魚介類やブランド肉などの高級食材を使用するとさらに上昇します。逆に、原価が安い野菜や炭水化物中心のメニューは低く抑えられます。味やボリュームとのバランスが重要なポイントです。
3位:ドリンク(アルコール・ソフトドリンク)の原価率
ドリンク類は原価率が非常に低く、飲食店にとって利益源となるジャンルです。
ソフトドリンクの原価率は5〜20%程度、アルコール類も10〜30%と安定しています。ウーロンハイなどの割材系は原価率が10%前後と非常に低く、一方でクラフトビールやワイン、日本酒などは30%を超えることがあります。
飲み放題メニューを組む際は、原価率の平均を25%以下に収める工夫が求められます。
まとめ|原価率の一覧で利益体質を強化
本記事では、原価率の計算式と粗利率との関係を整理し、飲食・小売・製造それぞれの平均値を確認したうえで、値付けやコスト削減に原価率一覧を生かす方法を解説しました。
各業界の数字を手元のデータと比べることで、自社の利益計画を精緻に描けるようになることをご理解いただけたと思います。ま
た、飲食店ではメニュー別の価格見直し、小売業では仕入条件の再交渉、製造業では歩留まりと労務費のバランス調整が重要です。