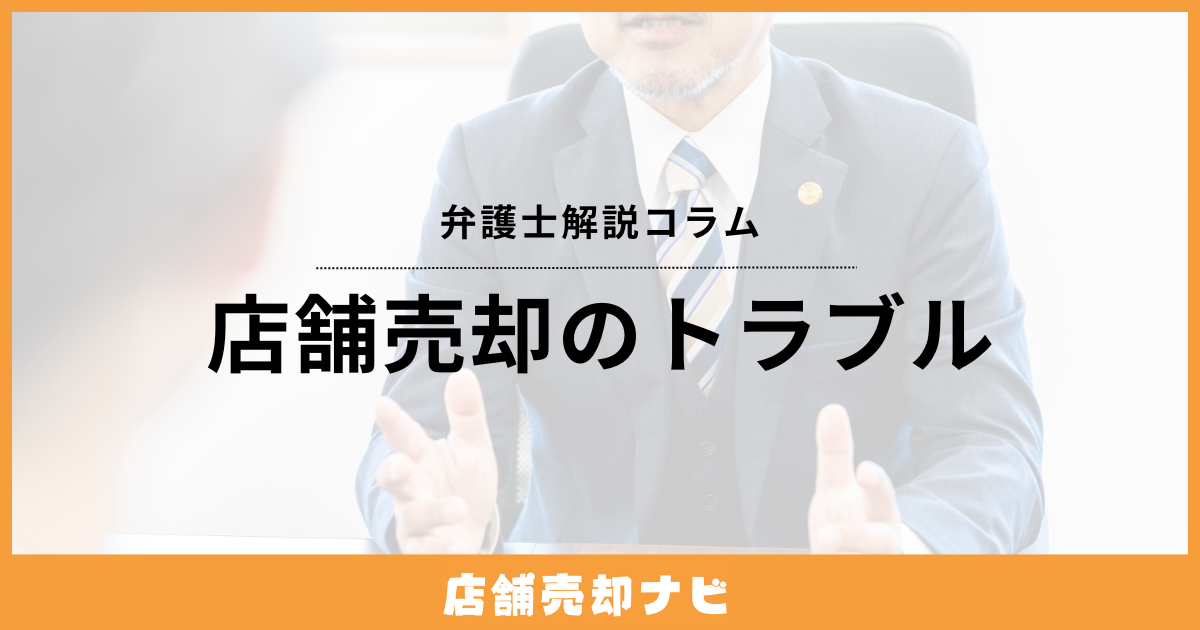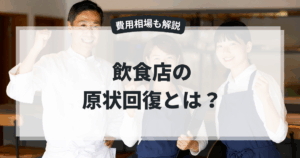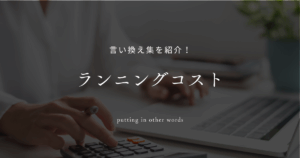飲食店や美容室などの店舗経営者にとって、「事業撤退」や「移転」は避けられない経営判断のひとつです。中でも、店舗設備や内装をそのまま引き継ぐ「居抜き譲渡」は、コストを抑えつつスムーズな撤退を実現できる方法として人気が高まっています。
しかし、表面的には「誰でも簡単にできそう」と思われがちな居抜き譲渡の裏側には、見落とされがちな重大なリスクが潜んでいます。
その中でも最も多く、かつ深刻なトラブルが「貸主(大家)からの承諾を得ずに店舗売却を進めてしまう」ケースです。本稿では、この貸主承諾なしでの店舗売却によって実際に生じたトラブル事例、法的観点からのリスク、そして具体的な予防策まで、弁護士監修のもとで詳しく解説いたします。
実際にあったトラブル:事前承諾を怠り、店舗売却が頓挫

東京都内で5年間営業していたある飲食店A店は、業績悪化と人材不足により閉店を決意し、内装・厨房設備を引き継ぐ形で「居抜き売却」を決断。知人を通じてB社(飲食店チェーン)に買い手が見つかり、譲渡価格300万円で合意。譲渡契約書も締結済みで、B社も開店準備を進めていました。
ところが、貸主である不動産管理会社からの“承諾”を得ていなかったことが発覚し、「借主(A店)が無断で契約外の第三者に使用させようとしている」として、譲渡に強硬に反対。結果的にB社は契約を白紙撤回し、A店は原状回復費用100万円超を負担して退去せざるを得ず、譲渡予定だった300万円も失いました。
なぜ貸主の承諾が必要なのか?
多くの店舗賃貸借契約では、借主が貸主の承諾なく第三者に店舗を「使用させる」ことを禁止する条項(いわゆる「転貸禁止条項」)が定められています。
この「使用させる」行為には、名義変更・居抜き譲渡・営業権譲渡・事業譲渡のような形式も広く含まれると解釈されており、店舗の一体的な譲渡は転貸と同視されることが一般的です。
法的リスク:承諾なしで居抜き譲渡をするとどうなる?
(1)譲渡そのものの「無効」:貸主からの承諾が得られていない譲渡は、債務不履行や契約解除の原因となり得ます。
(2)違約金・損害賠償請求のリスク:営業開始準備を進めた譲渡先から損害賠償を請求される場合も。
(3)原状回復義務の強化:譲渡失敗によりスケルトン化など高額な撤退費用が発生する可能性があります。
トラブルを未然に防ぐために取るべき3つのステップ

- ステップ1:賃貸借契約書の確認
- ステップ2:貸主との事前協議・承諾取得
- ステップ3:譲渡契約書への「解除条項」明記
弁護士として数多くの居抜き店舗譲渡の相談を受けてきましたが、貸主(大家さん)からの事前承諾を得ずに進めた結果、トラブルに発展するケースは後を絶ちません。
撤退費用や損害賠償のリスクも
とりわけ飲食店や美容室などの現場では、「早く売りたい」「閉店準備で忙しい」といった事情から、法的な確認を後回しにしてしまうことが少なくありません。しかし、貸主の承諾がないまま進めた譲渡行為は、契約違反とされる可能性が高く、撤退費用や損害賠償といった深刻なリスクに直結します。
譲渡契約を締結する前に、必ず「この貸主は譲渡を許してくれるか?」「どんな条件が必要か?」を丁寧に確認しましょう。最近では、承諾料の発生や、譲渡相手の事業内容の審査を求められることも多くなっています。
トラブルを未然に防ぐ最大の方法は、貸主との早期協議と、譲渡契約書への解除条項の記載です。これらを怠ると、せっかく譲渡先が決まっても、貸主の一言で全てが白紙に戻ることになります。
法的な構造だけでなく、信頼関係と書面の整備こそが、スムーズな店舗売却のカギとなります。
おわりに:店舗譲渡は「法律」と「人間関係」の両立がカギ
今回のテーマである「貸主からの承諾を得ずに進める」ことは、その中でも最も避けるべき初歩的な落とし穴です。
売却を検討する段階で、必ず契約書を読み込み、貸主との協議を行い、専門の業者などに相談することが健全で円滑な店舗売却を実現する第一歩となります。