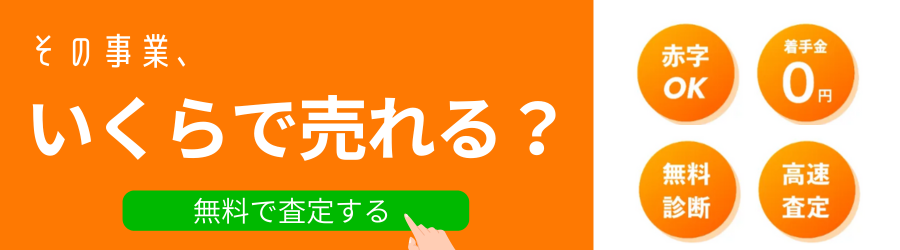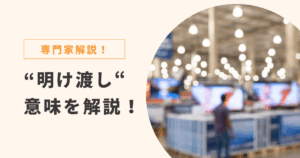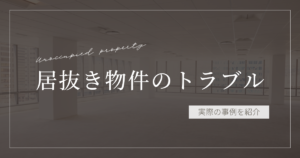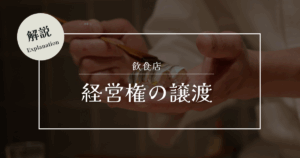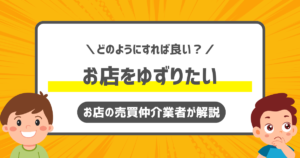「譲渡」と「売買」は似たように見えて、法的効果や税務処理が大きく異なります。
言葉を使い分けないまま契約書を作成すると、追加課税や所有権移転の不備など深刻なトラブルを招きかねません。この記事では民法の定義から実務上の手続き、典型的な失敗例までをまとめました。
このページでわかること
- 譲渡と売買の法律上の定義と要件
- 対価の有無で変わる契約形態の選び方
- 所得税・消費税・登録免許税の取り扱いの差
- 登記・登録を含む手続きの流れと期限
- トラブルを回避する契約条項チェックリスト
そもそも「譲渡」と「売買」とは?

譲渡は物や権利を他者へ移す行為全般を指し、代価の有無を問いません。一方で売買は代価の支払いを前提とした契約類型で、買主が代金を支払い、売主が目的物の所有権を移すことで成立します。
民法では売買を扱う555条が定められ、譲渡は債権譲渡(467条)や動産譲渡(178条)など対象ごとに条文が分散しています。
- 無償でも成立するか
- 所有権がいつ移るか
- 課税区分や税率の違い
- 登記・登録の必要性
民法上の位置づけを整理
契約類型を迷わず選ぶために、条文構造で大枠を押さえましょう。
| 類型 | 根拠条文 | 代価要件 | 代表的手続き |
|---|---|---|---|
| 売買 | 民法555条 | 必ず有償 | 所有権移転・契約不適合責任 |
| 譲渡(債権・動産など) | 民法467条、178条 ほか | 有償・無償いずれも可 | 通知・占有改定など対抗要件 |
売買は577条以下で責任関係が詳細に規定されるのに対し、譲渡は対象ごとに条文が分かれるため、読み違えが生じやすい点が要注意です。
日常会話と法律用語のギャップ
普段の言い回しと契約書の語義がずれると、手続きや課税が変わります。
- 「譲った」
↳無償の場合も含む - 「売った」
↳代金を受け取った事実を示唆 - 「あげた・もらった」
↳贈与契約を指す場合が多い
ドラフトでは「Price」「Consideration」など英語を併記すると、多言語契約でも誤解を減らしやすくなります。条文や通達番号を添えると後の税務調査にも対応しやすくなります。
譲渡に含まれる無償・有償のバリエーション
譲渡はひと言で済ませられないほど多様で、課税や手続きが大きく変わります。
| パターン | 主な税目 | 手続きの要点 |
|---|---|---|
| 無償譲渡(贈与) | 贈与税・登録免許税 | 贈与契約書の作成、登記(不動産) |
| 有償譲渡(売買・交換) | 所得税・消費税 | 売買契約書、代金支払、確定申告 |
| 条件付譲渡 | 状況によって変動 | 条件成就時に所有権を移転 |
| 信託型譲渡 | 受益者課税など | 信託契約書、受益権の登記 |
「対価の発生条件」と「所有権を移す時点」を分けて定義すると、税務と手続きのズレを抑えやすくなります。契約条項で責任範囲を明文化し、支払遅延や取消し時の対応まで盛り込むと安心です。

譲渡と売買の5つの違い

譲渡と売買は「権利を移す行為」という共通項がある一方で、契約書に落とし込む際には五つの観点を押さえると誤解を避けやすくなります。以下で実務で迷いやすいポイントを整理します。
対価の有無と価格決定
最初に注目したいのが支払われる対価の扱いです。対価があるかどうか、どのように決めるかによって契約類型は変わります。
| 項目 | 譲渡(有償・無償) | 売買 |
|---|---|---|
| 対価 | 設定してもしなくても可 | 必須 |
| 価格決定 | 双方の合意で自由 | 市場価格を参考に合理性が求められやすい |
| 税務署の視点 | 無償なら贈与税の対象になり得る | 時価と大きく乖離すると寄附認定リスクが高まる |
対価がゼロ、または著しく低い場合は贈与や寄附と扱われる恐れがあります。価格設定の意図を社内決裁書などで記録しておくと安心です。
権利・義務の移転タイミング
所有権やリスクがいつ移るかは在庫評価や保険負担を左右するため要注意です。
- 譲渡
↳契約当事者が合意した瞬間に所有権が移ることが多いが、引渡しと分離させる条項も設定できる - 売買
↳原則として代金支払いと同時、または引渡し時に移転。利害関係人への対抗要件も確認が必要 - 留保条項
↳動産売買では代金完済まで所有権を売主が保持する特約が一般的
倉庫内保管や運送中の事故リスクをどう分担するかは、移転タイミングの設定次第で大きく変わります。
税務上の取扱い(所得税・消費税)
税目は契約類型によって異なるため、支払総額や申告の工数が変わります。
| 項目 | 譲渡 | 売買 |
|---|---|---|
| 所得区分 | 譲渡所得・一時所得 など | 事業所得・譲渡所得 |
| 消費税 | 課税対象かは資産区分に依存 | 原則課税(非課税資産を除く) |
| 登録免許税 | 不動産・登記対象資産のみ | 不動産売買では譲渡と同率 |
同じ金額でも課税区分が違えば実効税率が変わるため、契約書に取得価額や用途を明記しておくと、税務署への説明がスムーズです。
登記・登録など手続きの相違
権利移転の公示には登記や登録が必要ですが、資産や契約類型によって要否が変わります。
- 不動産
↳登記が義務ではないものの、第三者対抗要件として実務上必須 - 動産譲渡
↳譲渡登記ファイルや占有改定で第三者に対抗可能 - 特許・商標
↳特許庁への変更登録が必要。売買も譲渡も同様 - 株式
↳株主名簿書換えのみで足り、商業登記は不要
手続き漏れは権利帰属を証明できず、二重譲渡時に優劣で不利になるため、登記完了証や登録完了通知の取得まで責任部署を定めましょう。
契約不適合責任の範囲
目的物が約束どおりの品質でなかった場合の責任範囲を比較します。
| 論点 | 譲渡 | 売買 |
|---|---|---|
| 規定条文 | 包括規定はなく、個別合意へ委ねられる部分が大きい | 民法577条〜584条 |
| 瑕疵の扱い | 特約で責任を限定することが多い | 買主が追完・代金減額・損害賠償などを求められる |
| 時効 | 契約で別段の定めがなければ一般の不法行為期間 | 目的物の種別に応じ短期消滅時効が適用 |
譲渡は条文の空白が多いため、責任範囲を詳細に書き込まないと立証や回収が難航しがちです。売買契約なら条文に沿った定型条項を利用し、リスクを定量化しやすい点がメリットとなります。
契約書に盛り込むべき譲渡売買契約のチェックリスト

譲渡や売買の契約は、条項を網羅的に整えれば移転手続きや税務申告が滑らかになります。この章では実務で抜けやすいポイントを洗い出し、条項ごとの着眼点を整理します。読者は自社の取引内容に合わせて条文を選び、ダブルチェックに役立ててください。
目的物の特定と範囲
契約書は「何を移すのか」をはっきりさせることで紛争を抑えられます。下の表で資産タイプ別の要確認項目を整理しました。
| 資産タイプ | 例 | 明確化すべき要素 |
|---|---|---|
| 不動産 | 土地・建物 | 地番、面積、付属設備、権利負担 |
| 動産 | 機械設備、在庫 | 製造番号、数量、現況写真、保証書 |
| 権利 | 株式、債権 | 銘柄・数、残額、担保設定の有無 |
| 無形資産 | ソフトウェア、ライセンス | バージョン、利用範囲、アップデート権 |
表に沿って条文を作ると、後日の「聞いていない」といった主張を防ぎやすくなります。
対価と支払条件
金額と支払い方法は紛争の火種になりやすい項目です。まずは押さえるべきチェックポイントを順にまとめます。
- 決定方法
↳時価、簿価、独立評価など根拠を明記 - 支払時期
↳一括、分割、マイルストーン連動など選択肢を整理 - 通貨と送金手段
↳円建て・外貨建て、銀行振込・送金アプリなどを固定 - 遅延損害金
↳利率・起算日・遅延通知の手順を規定
上記を押さえることで、資金繰り計画や税務処理のブレを抑えられます。
表明保証と免責条項
目的物が想定どおりでないときの責任範囲を決める条文です。代表的な内容を対比で整理しました。
| 論点 | 表明保証 | 免責条項 |
|---|---|---|
| 目的 | 現状に関する事実認定 | 売主の責任限度を設定 |
| 典型的文言 | 「第三者の権利侵害がない」 | 「本契約で定める以外の責任を負わない」 |
| 救済手段 | 損害賠償・解除 | 賠償上限・通知期限 |
両者はセットで整理するとバランスが取りやすく、買主の安心感と売主のリスク管理を両立できます。
秘密保持・競業避止
取引後も続く守秘義務や競業制限は、ビジネスの継続性を守るうえで欠かせません。押さえるべき要素は次のとおりです。
- 秘密情報の範囲
↳技術情報・顧客データ・価格表などを列挙 - 開示先の限定
↳関連会社や専門家への開示条件を規定 - 競業制限の期間
↳業種と地域を限定し、公正取引委員会ガイドラインも参照 - 違反時の措置
↳損害賠償、差止め請求、違約金などを設定
範囲を過度に広げると無効のリスクが高まるため、合理的かつ必要最小限に絞りましょう。
まとめ|違いを理解してトラブルを未然に防ごう
譲渡と売買はどちらも権利を移す行為ですが、対価の有無・税務区分・登記手続きなどで要件が大きく変わります。この記事では民法上の位置づけを整理し、対価設定や所有権移転のタイミング、税負担の計算方法、必要条項の書きぶりまで順を追って解説しました。
その結果、読者は自分の取引目的に応じて「譲渡」か「売買」かを選び、条文に根拠を持たせながら契約書を作成するための視点を得られたはずです。
実務では、①目的物の範囲と価値を明確化し、②対価と支払時期を合意し、③所有権移転時点とリスク分担を条項で押さえ、④登記や登録を期限内に済ませ、⑤税申告を漏れなく行う――という流れが安全な着地につながります。