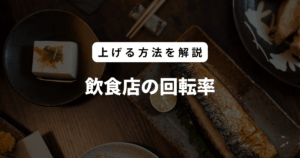売上は伸びているのに利益が思うように残らない――そんなとき真っ先に見直したいのが「原価率」です。業種ごとの平均値と自社の数字を照らし合わせれば、価格が高すぎるのかコストがかさみすぎているのかがはっきりわかります。
そこで本記事では飲食・小売・製造・サービスの代表的な原価率を一覧で整理し、利益計画や値付けにすぐ役立つ考え方を解説します。
このページでわかること
- 原価率の定義と計算式の押さえどころ
- 飲食・小売・製造・サービス業の平均原価率一覧
- 原価率を使った利益計画と値付けの組み立て方
【業種別】原価率一覧と平均

原価率は「売上原価 ÷ 売上高 × 100」で求められ、売上高に占めるコストの割合を数量化できる指標です。中小企業庁がまとめた全産業平均は74.56%で、業種によって開きがあります。
一覧化して自社の数字と照らし合わせれば、値付けに問題があるのか、それとも仕入や製造コストが膨らんでいるのかが判断しやすくなります。売上総利益率(粗利率)と表裏一体の指標でもあるため、この章では計算式を整理したうえで代表的な業界平均を確認しましょう。
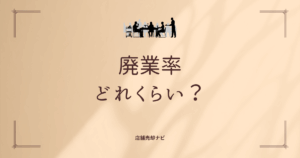
原価率の定義と計算式
まずは原価率と粗利率の関係を整理します。
| 指標 | 計算式 | 読み方 |
|---|---|---|
| 原価率 | (売上原価 ÷ 売上高) × 100 | 売上に対してコストが何%か |
| 売上総利益率 | 100 − 原価率 | 売上に対して粗利が何%か |
たとえば仕入原価が720円で販売価格が1,200円の商品であれば、原価率は60%、粗利率は40%となります。このように両指標を同時に追うことで、原価を削減するのか販売価格を調整するのかを具体的に検討できます。
業界・業種ごとの平均原価率早見表
公的統計(令和5年速報)から主要業種を抜粋しました。
| 業種 | 平均原価率 | 出典 |
|---|---|---|
| 宿泊・飲食サービス | 36.68% | 中小企業実態基本調査 |
| 小売業 | 69.58% | 同上 |
| 製造業 | 79.27% | 同上 |
| 情報通信業 | 52.40% | 同上 |
数値は企業規模や商品構成、季節要因で変動します。平均とかけ離れていても即断は避け、まずは同規模・同業態と比較したうえで改善策を検討しましょう。
原価率が高すぎる/低すぎる場合の影響
適正幅を外れると、資金繰りや顧客満足にまで波及します。主なリスクを整理しました。
- 高原価率(平均を上回る)
↳ 利益が圧迫され資金繰りが厳しくなりやすく、値上げに踏み切れず成長余力が縮小します - 低原価率(平均を下回る)
↳ 品質やサービスレベルが低下する恐れがあり、顧客離れを招く懸念が高まります - 変動原価率(季節で大きくブレる)
↳ 繁忙期の高値仕入と閑散期の値崩れで利益曲線が荒れ、資源配分が難しくなります
原価率は一度チェックして終わりではありません。メニューや商品構成が変わるたびに推移を追い、月次あるいは週次で改善策の効果を測定する姿勢が重要です。
原価率の一覧の使い方|価格戦略を設計する

業界平均を一覧で把握したあとは、自社の原価率と照合して売価の修正かコスト削減かを決め、どの手順で行うかを描く必要があります。飲食・小売・製造の三業種を例に、原価率一覧を実務へ落とし込む方法を整理しましょう。

飲食店:メニュー価格の見直し
代表メニューを洗い出し、原価率の高低で優先順位を決めます。主な流れは次のとおりです。
- 現状把握 — POSデータを用いてメニュー別原価率を算出します
- 値付け候補を試算 — 目標粗利率から逆算して新しい販売価格を計算します
- 代替素材・ポーションを検証 — 品質を損なわずに原価を抑えられるか検証します
- 試食とスタッフ教育 — 味とボリュームに関する変更点を共有し、接客トークを整えます
- 告知と価格改定 — 改定理由を明確に伝え、改定日を周知します
数字と味の両面を押さえたうえで、調理担当者とホールスタッフが協力して価格改定を実施しましょう。
小売業:仕入原価の最適化
同じ売価でも仕入れ条件が1%変われば利益は大きく動きます。下表に、小売店でよく採られる施策をまとめました。
| 施策 | 具体例 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 数量ディスカウント交渉 | 月間発注量を提示し単価を再設定 | 仕入原価を即時圧縮 |
| 仕入先統合 | 同カテゴリ商品を上位3社から1社へ集約 | 物流費と発注管理の軽減 |
| 共同購買 | 同業グループで共同発注 | スケールメリットによる単価低減 |
| リードタイム短縮 | 国内在庫を持つ卸へ切替 | 過剰在庫と値下げリスクの抑制 |
施策は単独でも機能しますが、複数を組み合わせると効果が乗算的に広がります。導入前後で原価率を比較し、改善幅を数値で確認することが欠かせません。
製造業:材料費と労務費のバランス
製造業では材料費だけでなく労務費も原価率を左右します。次の観点でバランスを整えましょう。
- 歩留まりの改善
↳ 加工工程のロス削減で材料費を圧縮します - ライン編成の見直し
↳ 熟練者を要所に配置し、作業時間を短縮します - 標準作業書の更新
↳ 作業のばらつきを抑え、再加工の発生を防止します - 設備投資の投資対効果計算
↳ 自動化装置導入による労務費削減を検証します
材料費が下がっても手待ちが増えれば原価率は戻ってしまいます。歩留まりと稼働率を同時に管理し、投資判断は削減見込み額と回収期間を明確にしたうえで進めると成果が定着しやすくなります。
まとめ|原価率の一覧で利益体質を強化
本記事では、原価率の計算式と粗利率との関係を整理し、飲食・小売・製造それぞれの平均値を確認したうえで、値付けやコスト削減に原価率一覧を生かす方法を解説しました。
各業界の数字を手元のデータと比べることで、自社の利益計画を精緻に描けるようになることをご理解いただけたと思います。また、飲食店ではメニュー別の価格見直し、小売業では仕入条件の再交渉、製造業では歩留まりと労務費のバランス調整が重要です。
実践にあたっては、まず現在の原価率を月次で点検し、目標とする粗利率を決めたうえで、値付けの修正か仕入・工程の見直しかを判断してください。改善策を実行した後は、データで効果を検証し、必要に応じて再調整するサイクルを続けることで、利益体質が安定します。